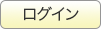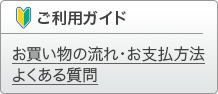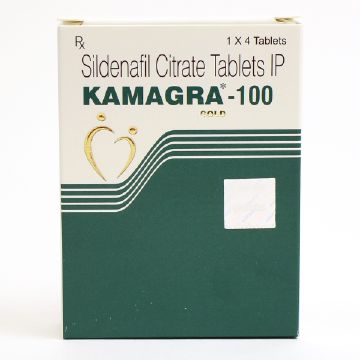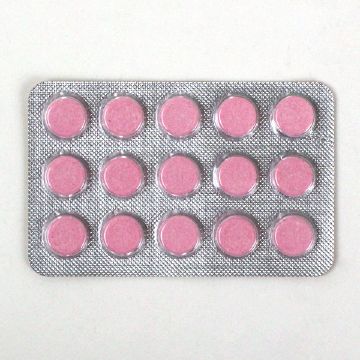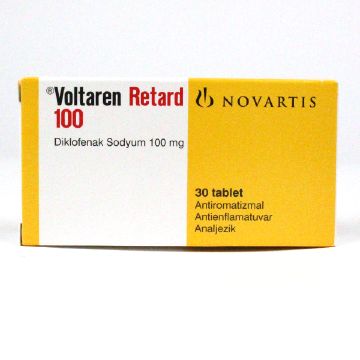オカメット500mg通販|医療ダイエット痩せ薬|最安値1錠34円
オカメット500mg商品写真は製薬会社の都合により、実際に届く商品とパッケージ等が異なる場合があります。
医薬品の効果や品質に違いはありませんのでご安心下さい。
病院での処方と同様に、シートごとのお渡しとなる場合もございますので、予めご了承下さい
タイミングにより使用期限が前後する場合がございます。
掲載の使用期限はあくまで目安とし、必ずしも掲載の使用期限の商品がお届けとなることを保証するものではありませんので、予めご了承ください。
オカメット500mgとは
オカメット500mgは、メトホルミン塩酸塩を有効成分とする糖尿病治療薬です。
血糖値のコントロールが難しい糖尿病患者に広く使用されており、近年では血糖値を安定させることからダイエットや生活習慣病予防の側面でも注目されています。
主に2型糖尿病の治療に用いられ、特に食事療法や運動療法だけでは十分な効果が得られない場合に、血糖値を適正な範囲内にコントロールする目的で使用されています。
オカメット500mgの特徴
- 低血糖リスクが少ない
- ダイエットやメタボ対策に有効
- 世界中で使用され、実績のある成分
- 他の糖尿病薬に比べ、低価格
オカメット500mgはこのような方におすすめ
- 食後の血糖値の急激な上昇が気になる方
- インスリン抵抗性があり、体重管理に苦労している方
- メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防を考えている方
- 食事や運動療法だけで血糖値のコントロールが難しい方
注意事項
重篤な乳酸アシドーシスを起こすことがあり、死亡に至った例も報告されています。
乳酸アシドーシスを起こしやすい方には服用はしないでください。
また、腎機能障害や肝機能障害のある方、高齢者が服用する場合には、定期的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に服用してください。
特に75歳以上の高齢者では、服用を慎重に判断してください。
効果効能
食後の急激な血糖値の上昇を抑えることで、過剰なインスリン分泌が防げます。
これにより脂肪蓄積を抑え、空腹感を感じにくくするため、食べ過ぎ防止やダイエット効果が期待できます。
また、メトホルミンはインスリンの分泌を直接刺激しないため、低血糖を起こしにくいという特徴があります。
オカメット500mg(メトホルミン塩酸塩)の作用機序
メトホルミンは、血糖値を下げるために3つの働きをします。
-
肝臓での糖新生の抑制
肝臓は血糖値が下がった時に、身体のエネルギーを補うために糖を新たに作る「糖新生(とうしんせい)」という働きを持っています。
しかし、この糖新生が過剰に働くと、食事をしていない時でも血糖値が高くなりやすくなります。メトホルミンはこの糖新生を抑制することで、空腹時血糖の上昇を防ぎ、1日の血糖値のバランスを整える役割を果たします。
-
筋肉や脂肪細胞での糖の利用促進
血糖値が高いにもかかわらず、細胞が糖をうまく取り込めない「インスリン抵抗性(インスリンが効きにくくなる状態)」があると、血糖値がさらに上がってしまいます。メトホルミンは筋肉や脂肪細胞に働きかけて、血液中の糖を効率よく取り込ませ、エネルギーとして活用しやすくします。
この作用により、インスリンの感受性が改善され、血糖値の正常化が期待されます。
身体全体の代謝も促進される効果があります。
-
腸管からの糖吸収抑制
食事で摂取した糖は、腸管から血液中に吸収されて血糖値を上昇させますが、メトホルミンはこの糖の吸収速度を緩やかにします。
その結果、食後の急激な血糖値の上昇が抑えられ、インスリンの過剰な分泌も防ぐことができます。
また、緩やかな糖吸収により、長時間にわたりエネルギーが安定して供給されるため、空腹感の抑制や過食防止にも繋がります。
オカメット500mg(メトホルミン塩酸塩)の適応症
-
2型糖尿病
2型糖尿病は、インスリンの分泌量が不足したり、インスリンがうまく効かなくなることで血糖値が高くなる疾患です。
オカメット500mgは、食事療法や運動療法を行っても血糖コントロールが難しい場合に服用されます。
特に肥満型の2型糖尿病の方において、インスリン抵抗性を改善する効果が高いため、より効果的に血糖値を正常範囲に維持することができます。
-
インスリン抵抗性を伴う症状
メトホルミンは、メタボリックシンドロームや多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)など、インスリン抵抗性が関わる症状にも用いられることがあります。
これらの症状では、インスリンが効きにくくなることで血糖値が上昇しやすく、代謝異常を引き起こします。
オカメット500mgは、インスリンの感受性を高め、血糖値の改善とともに、これらの関連疾患の予防や症状の軽減に効果がある可能性があります。
使用方法
以下の服用方法を守ってご使用ください。
オカメット500mgの飲み方(用法・用量)
| 1日の用量 ※効果や体調により適宜増量 |
【初期用量】 1日500mg ※1錠を分割して服用してください。 【維持用量】 1日750mg〜1500mg(1.5錠~3錠) 【最大用量】 1日2250mg(4.5錠)まで |
|---|---|
| 服用回数 | 1日2~3回 |
| 服用タイミング | 食後 |
| 服用時の飲料水 | 水またはぬるま湯 |
服用時のポイント
-
食後の服用がおすすめ
オカメット500mgは、胃腸への刺激を和らげるために、食後に服用することが推奨されています。
食事のすぐ後に服用することで、薬剤が胃腸に与える負担を軽減し、副作用の発生リスクを抑えることができます。
また、食後の血糖値の上昇を効果的に抑制するためにも、食後のタイミングがおすすめです。
-
服用は少量から始める
副作用を最小限に抑えるため、まずは低用量から服用を開始することが推奨されます。
特に胃腸障害(吐き気や下痢など)が現れやすいため、身体が薬剤に慣れるように少しずつ用量を増やしていきます。
効果や体調により、徐々に適切な量に調整しましょう。
-
服用を忘れた場合
もし服用を忘れた場合は、気付いた時点ですぐに1回分を服用してください。
ただし、次の服用時間が近い場合は、忘れた分は飲まずに1回分を飛ばすようにしましょう。
決して2回分をまとめて服用しないでください。
過剰摂取による副作用のリスクがありますので注意が必要です。
服用頻度
オカメット500mgは、1日2~3回服用してください。
副作用
オカメット500mgの副作用は、通常軽度で一過性のものが大半ですが、観察を十分に行い、異常が認められた場合には服用を中止するなど適切な対応を行ってください。
オカメット500mgの重大な副作用
- 乳酸アシドーシス
- 低血糖
- 肝機能障害
- 黄疸
- 横紋筋融解症
その他の副作用
| 消化器 | 下痢、悪心、食欲不振、腹痛、嘔吐、消化不良、腹部膨満感、便秘、胃炎、胃腸障害、放屁増加 |
|---|---|
| 血液 | 貧血、白血球増加、好酸球増加、白血球減少、血小板減少 |
| 過敏症 | 発疹、そう痒 |
| 肝臓 | 肝機能異常 |
| 腎臓 | BUN上昇、クレアチニン上昇 |
| 代謝異常 | 乳酸上昇、CK上昇、血中カリウム上昇、血中尿酸増加、ケトーシス |
| その他 | めまい、ふらつき、全身倦怠感(※1)、空腹感、眠気、動悸、脱力感、発汗、味覚異常、頭重、頭痛、浮腫、ビタミンB12減少(※2)、筋肉痛(※1) |
(※1)乳酸アシドーシスの初期症状である可能性があるので注意してください。
(※2)長期使用により、ビタミンB12の吸収不良があらわれることがあります。
禁忌
以下の項目に該当する方は、オカメット500mgを服用できません。
- 乳酸アシドーシスの既往のある方
- 重度の腎機能障害(eGFR 30mL/min/1.73m2未満)のある方または透析をしている方
- 重度の肝機能障害のある方
- 心血管系、肺機能に高度の障害(ショック、心不全、心筋梗塞、肺塞栓など)のある方及びその他の低酸素血症を伴いやすい状態にある方
- 脱水症の方または脱水状態が懸念される方(下痢、嘔吐などの胃腸障害のある方、経口摂取が困難な方など)
- 過度のアルコール摂取者
- 重症ケトーシス、糖尿病性昏睡または前昏睡、1型糖尿病の方
- 重症感染症、手術前後、重篤な外傷のある方
- 栄養不良状態、飢餓状態、衰弱状態、脳下垂体機能不全または副腎機能不全の方
- 妊婦または妊娠している可能性のある女性
- 本剤の成分(メトホルミン塩酸塩)またはビグアナイド系薬剤に対し過敏症の既往歴のある方
併用禁忌
併用すると重篤な副作用が発生する場合がありますので、オカメットとの併用はお控えください。
アルコール(過度の摂取)
乳酸アシドーシスを起こすことがあります。
オカメット服用中は過度のアルコール摂取(飲酒)を避けてください。
併用注意
以下の薬剤と併用する際は、ご注意ください。
乳酸アシドーシスを起こすことがある薬剤
以下の薬剤との併用により乳酸アシドーシスを起こすことがあります。
ヨード造影剤
腎機能が低下すると、オカメット(メトホルミン塩酸塩)の排泄が遅れ、乳酸アシドーシスを引き起こす原因になると考えられます。
ヨード造影剤を用いて検査を行う場合には、オカメットの服用を一時的に中止してください。
腎毒性の強い抗生物質
- ゲンタマイシン など
腎機能が低下すると、オカメット(メトホルミン塩酸塩)の排泄が遅れ、乳酸アシドーシスを引き起こす原因になると考えられます。
併用する場合は、オカメットの服用を一時的に減量・中止するなど適切な対応を行ってください。
利尿作用を有する薬剤
- 利尿剤
- SGLT2阻害剤 など
利尿作用のある薬剤を使用すると、体液量が減少して脱水状態になり、それが乳酸アシドーシスを引き起こす原因となる場合があります。
脱水症状があらわれた場合には、オカメットの服用を中止し、適切な対応を行ってください。
血糖降下作用を増強する薬剤
併用により低血糖が起こることがあります。
状態を十分観察しながら服用してください。
糖尿病用薬
- インスリン製剤
- スルホニルウレア剤
- 速効型インスリン分泌促進薬
- α-グルコシダーゼ阻害剤
- チアゾリジン系薬剤
- DPP-4阻害剤
- GLP-1受容体作動薬
- SGLT2阻害剤
- イメグリミン塩酸塩 など
併用により血糖降下作用が増強し、スルホニルウレア剤併用時に低血糖のリスクが増加するおそれがあります。
たん白同化ホルモン剤
機序は不明です。
サリチル酸剤
サリチル酸剤の血糖降下作用が低血糖の原因と考えられます。
β遮断剤
β遮断作用により、アドレナリンを介した低血糖からの回復を遅らせることが原因と考えられます。
モノアミン酸化酵素阻害剤
モノアミン酸化酵素阻害剤によるインスリン分泌促進や糖新生抑制が低血糖の原因と考えられます。
血糖降下作用を減弱する薬剤
併用により血糖降下作用が減弱することがあります。
状態を十分観察しながら服用してください。
アドレナリン
アドレナリンは末梢での糖利用を抑制し、肝での糖新生を促進し、インスリン分泌を抑えることで、血糖降下作用を減弱すると考えられます。
副腎皮質ホルモン
副腎皮質ホルモンによる肝での糖新生促進などが、血糖降下作用を減弱する原因と考えられています。
甲状腺ホルモン
甲状腺ホルモンは糖代謝全般に作用し、血糖値を変動させることで血糖降下作用を減弱すると考えられています。
卵胞ホルモン
卵胞ホルモンは耐糖能を変化させ、血糖を上昇させることで血糖降下作用を減弱すると考えられています。
利尿剤
利尿剤によるカリウム喪失により、インスリン分泌が低下することが血糖降下作用を減弱すると考えられています。
ピラジナミド
機序は不明です。
イソニアジド
イソニアジドによる炭水化物代謝阻害が、血糖降下作用を減弱する原因と考えられています。
ニコチン酸
ニコチン酸による血糖上昇作用が、血糖降下作用を減弱する原因と考えられています。
フェノチアジン系薬剤
フェノチアジン系薬剤はインスリン分泌を抑制し、副腎からのアドレナリン遊離を促進することで、血糖降下作用を減弱すると考えられています。
OCT2、MATE1、またはMATE2-Kを阻害する薬剤
- シメチジン
- ドルテグラビル
- ビクテグラビル
- バンデタニブ
- イサブコナゾニウム硫酸塩
- ピミテスピブ など
オカメット(メトホルミン塩酸塩)の血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがあります。
観察を十分に行い、必要に応じてオカメットを減量するなど慎重に服用してください。
イメグリミン塩酸塩
消化器症状の発現に注意してください。
特に併用初期に多く発現する傾向が認められています。
保管方法
-
高温、多湿、直射日光を避けてください
医薬品は、光や温度、湿度など外的要因によって効能が落ちる可能性があります。
特に指示がない場合は、直射日光や高温を避けて、室温(1~30℃)で保管してください。
-
冷所での保存は避けてください
特に冷所保存の指示がない場合、冷蔵庫で保管する必要はありません。
-
子どもの手の届かないところに保管してください
子どもの誤飲を防ぐため、手の届かない高いところなどに保管してください。
また、子どもの目を引く様なお菓子の缶などで保管しないよう注意してください。
-
期限の切れた薬剤は使用を控えてください
医薬品の使用期限は必ず守ってください。
使用期限が過ぎた医薬品は、効果が落ちてしまったり、思わぬ副作用が発生する場合があります。
服用前に使用期限を確認してからご使用ください。
-
容器の入れ替えはお控えください
それぞれの医薬品に応じて包装に工夫がされていますので、シートから出したり、別の容器に移し替えて保管しないでください。
中身や使用方法がわからなくなってしまう場合があります。
誤用を防ぐためにも、元の容器のままご使用ください。
-
医薬品以外のものと一緒に保管しないでください
食品などと一緒に保管すると、誤用してしまう恐れがあります。
-
余った医薬品は、適切に処分してください
飲み残したものや期限が切れた医薬品は、処分してください。
処分方法に不安がある場合は、薬剤師に相談してください。
参考サイト
当商品ページは、これらのサイトを参考として制作しております。
医療用医薬品 : メトグルコ - KEGG
よくあるご質問(FAQ)
-
質問:メルビンのジェネリック薬品は?回答:メルビン(有効成分:メトホルミン塩酸塩)は、ビグアナイド系の経口血糖降下薬として広く使用されていますが、ジェネリック医薬品も多数発売されており、コストを抑えつつ同等の効果が得られます。
代表的な製品名には、メトホルミン塩酸塩錠250mg・500mg・1000mg(日医工、サンド、東和薬品、キョーリン、日本ジェネリックなど製造)、および徐放錠タイプのメトホルミン塩酸塩徐放錠(大鵬、エーザイ、沢井製薬など)があります。
保険適用下では先発品の約半額程度で処方可能で、自己負担3割の場合、250mg錠なら月数百円から利用できます。
即放性錠と徐放性錠が選択でき、即放性は速効性、徐放性は胃腸障害軽減と一日一回投与が魅力です。
処方の際は、ライフスタイルや忍容性を考慮し、用量・剤形を医師と相談のうえ決定してください。 -
質問:メトホルミンはなぜ若返りに効くのか?回答:メトホルミンはビグアナイド系薬剤で、AMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)を活性化し、肝臓における糖新生抑制や末梢組織のインスリン感受性改善をもたらします。
AMPKの活性化はmTORシグナル経路を抑制し、オートファジー(細胞内自己消化作用)を促進することで、損傷したタンパク質や異常ミトコンドリアの除去を促します。
その結果、細胞老化のマーカー低下やミトコンドリア機能改善が観察され、動物実験では寿命延長効果、人の観察研究では心血管リスク低減や老化関連疾患発症抑制が示唆され、「若返り薬」としての可能性が注目されています。 -
質問:メトホルミンとリベルサスどちらが痩せますか?回答:メトホルミンは主に肝臓での糖新生抑制とインスリン抵抗性改善作用を有し、単剤使用での体重変化は平均2~3kg程度の減少にとどまります。
これに対してリベルサス(経口セマグルチド)はGLP-1受容体作動薬で、視床下部の食欲中枢を刺激し満腹感を増強することで、臨床試験では10%以上の体重減少が認められています。
したがって、体重減少効果のみを比較するとリベルサス圧倒的に優れますが、副作用の頻度や費用、適応疾患の相違点を考慮したうえで、最適な治療薬を選択する必要があります。 -
質問:エクメットの一日の摂取量は?回答:エクメット(メトホルミン塩酸塩製剤)の標準的な投与法は、まず500mgを1日2回(計1,000mg)を食後に服用し、忍容性を確認します。
その後、1~2週間ごとに500mgずつ漸増し、最低でも4週間以上かけて副作用(悪心・下痢など)の有無を観察しながら調整します。
最終的な維持用量は1日2,000~2,250mgまで認められており、多くの患者で血糖降下効果が最大化します。
ただし、腎機能(eGFR)30mL/分/1.73m未満や重度の機能障害例では使用禁忌、30~45未満では慎重投与とされるため、投与前に必ず腎機能検査を行い、定期的にモニタリングを実施してください。 -
質問:メルビンの一般名は?回答:メルビンの一般名は「メトホルミン塩酸塩」です。
メトホルミン塩酸塩はビグアナイド系経口血糖降下薬で、主に肝臓の糖新生抑制と筋肉や脂肪組織でのインスリン感受性を改善することで血糖値を低下させます。
食後高血糖やインスリン抵抗性の強い2型糖尿病患者に適応され、初期用量は250~500mgを1日2回、食後または食直前に服用し、最大用量は1日2,250mgです。
腎機能が低下した場合はeGFRを評価し、用量調整や休薬を検討する必要があります。
副作用として消化器症状(下痢、悪心、腹部膨満感)やビタミンB12欠乏、まれに乳酸アシドーシスが報告されるため、定期的に血液検査やビタミンB12測定を行い、安全性の確認をしながら継続投与します。 -
質問:メトホルミンとメトグルコは同じものですか?回答:メトグルコは「メトホルミン塩酸塩」を有効成分とする製品名であり、エクメットやグリコランなど他の製剤と成分、作用機序、副作用プロファイルは完全に同一です。
主作用は肝臓の糖新生抑制と末梢組織のインスリン感受性改善で、2型糖尿病の血糖コントロールに用いられます。
剤形は徐放錠と即放錠の2種類があり、吸収速度や血中濃度曲線に差があるものの、臨床的効果や安全性には差がありません。
腎機能に応じた用量調整や定期的な血液検査が重要な点も同じです。 -
質問:メルビンとメトグルコの違いは何ですか?回答:メルビンとメトグルコは、いずれも有効成分「メトホルミン塩酸塩」を含むビグアナイド系血糖降下薬ですが、製剤設計と添加物に差があります。
メルビンは即放性錠で速やかに血中濃度を上昇させる設計、メトグルコは徐放性(持続放出)錠で穏やかに長時間にわたり血中濃度を維持する設計です。
即放性は食後急性期の血糖降下に優れ、徐放性は胃腸障害を軽減しつつ一日一回投与が可能です。
また、製造会社ごとに錠剤の大きさや基剤(添加物)、吸収挙動に微妙な違いがあるため、患者のライフスタイルや忍容性に合わせて選択されます。
いずれも主作用は肝臓の糖新生抑制および末梢組織のインスリン感受性改善で同等の血糖降下能を有しています。 -
質問:メトホルミンと一緒に飲んではいけない薬は?回答:メトホルミン塩酸塩と併用注意または禁忌とされる薬剤には、以下の薬剤があげられます。
* ヨード造影剤(検査前後48時間の一時休薬が必要)
* 利尿薬・ACE阻害薬・NSAIDs(腎血流低下でメトホルミン排泄が遅れ、乳酸アシドーシスリスク増大)
* アルコール大量摂取(乳酸産生亢進)
* シメチジンやベラパミル(メトホルミンの血中濃度上昇)
また、重度肝機能障害や心不全治療薬との併用も注意を要します。
併用薬の有無は必ず医師・薬剤師に報告してください。 -
質問:メトホルミンが中止になった理由は何ですか?回答:メトホルミン塩酸塩製剤は長期にわたり安全性が確立されていますが、一部の製造ロットで発がん性の疑いがある不純物「NDMA(N-ニトロソジメチルアミン)」が検出されたため、該当ロットは回収・販売中止となりました。
厚生労働省は全製造販売業者に対し、原薬・製剤の不純物検査および管理体制の強化を指示し、NDMA基準を下回る安全確認済み製品のみが市場に供給されるよう徹底されています。
現在は適正基準をクリアした製剤のみが流通しています。 -
質問:メトホルミンは体に良くない?回答:メトホルミンは2型糖尿病の第一選択薬として心血管イベント抑制や長寿効果が示唆され、高い安全性が認められています。
一方、副作用として胃腸症状(悪心・下痢・腹部膨満感)が約20%に見られ、ビタミンB12吸収障害による貧血や末梢神経障害、まれに乳酸アシドーシスをきたすリスクがあります。
特に腎機能低下例(eGFR<30mL/分/1.73m)や重度の・肝・呼吸不全では禁忌です。
適切な腎機能モニタリングと定期的な血液検査を行うことで、メリットを享受しつつ安全に使用できる薬剤です。 -
質問:メトホルミンの自費価格はいくらですか?回答:保険適用外の自由診療でメトホルミンを処方する場合、クリニックやオンライン診療によって異なりますが、月額3,000~5,000円が一般的です。
初回割引やまとめ買いプランを利用すると2,000~3,000円程度まで下がることがあります。
対して保険適用であれば自己負担は数百円~1,000円程度です。
自費診療では、診察料や配送手数料が別途かかる場合もあるため、総額を確認してクリニックを選ぶと良いでしょう。 -
質問:メトホルミンは75歳以上にはどうですか?回答:高齢者では加齢による腎機能低下や脱水リスクが高いため、投与前にeGFR(推算糸球体濾過率)を必ず評価します。
ガイドラインではeGFR30mL/分/1.73m未満で禁忌、30~45では慎重投与、45以上で通常投与が可能とされます。
75歳以上では初期用量を250mg/日程度から開始し、定期的に腎機能・乳酸アシドーシス兆候をモニタリングしながら用量調整を行うことで、安全に血糖コントロールを図れます。 -
質問:メトホルミンで何キロ痩せる?回答:メトホルミン塩酸塩はインスリン感受性を改善し、肝臓の糖新生を抑制することで血糖を下げるビグアナイド系薬ですが、体重減少効果はあくまで補助的です。
臨床試験や観察研究では、平均2~3kg程度の減量が得られると報告されています。
ただし、個人差が大きく、生活習慣(食事・運動)を併用しなければ十分な減量は困難です。
高用量(最大2,250mg/日)使用例ではやや減量幅が広がる傾向がありますが、胃腸障害のリスク増大も伴うため、初期は最低用量から開始し、3~6ヵ月を目安に体重推移を評価しつつ、生活習慣改善と組み合わせることが重要です。 -
質問:メトホルミンとフォシーガのどちらがいいですか?回答:メトホルミンは2型糖尿病の第一選択薬で、肝臓の糖新生抑制とインスリン感受性改善により心血管リスク低減も期待できますが、体重変化は平均2~3kg減にとどまります。
一方、フォシーガdapagliflozin)はSGLT2阻害薬で、糖と同時に水分も尿中に排泄し、平均3~4kgの減量効果に加え心不全・腎保護効果が示されています。
腎機能が保たれていればメトホルミン開始後の併用選択肢として優れます。
減量重視ならフォシーガ心血管イベント抑制ならメトホルミン、両者併用で相乗効果を狙うのが理想的です。 -
質問:一番痩せる糖尿病薬は何ですか?回答:現時点で最も優れた減量効果を示すのはGLP-1受容体作動薬です。
特に経口セマグルチド(リベルサスや注射製剤セマグルチド・デュラグルチドは、臨床試験で5~15%もの体重減少が報告され、肥満治療薬としての承認も得ています。
SGLT2阻害薬(フォシーガなど)は約3~4%、メトホルミンは約2~3%の減少、α-グルコシダーゼ阻害薬は体重中立であり、GLP-1受容体作動薬がダントツで最も強力とされています。 -
質問:防風通聖散で何キロ痩せた?回答:防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)は漢方処方の一種で、脂肪代謝促進や便通改善、利水作用を通じて体重減少をサポートします。
臨床研究では、軽度肥満者が食事・運動療法と併用した場合、平均1.0~2.0kgの減量が報告されています。
ただし、単剤では大幅減量は難しく、個人差も大きい点に留意が必要です。
作用機序には
* 腸管脂質吸収抑制
* 利水によるむくみ改善
* 末梢血流改善による新陳代謝亢進が挙げられます。
継続期間は最低8週間以上が望ましく、併用療法での減量効果と耐容性を定期的に評価して調整します。 -
質問:ヘモグロビンA1cがいくつになったら薬を飲むのですか?回答:日本の診療ガイドラインでは、HbA1c 6.5%以上で2型糖尿病と診断し、まずは食事・運動療法を行ったうえで、6.5%を超えた持続が認められれば薬物療法の開始を検討します。
ただし、心血管リスクが高い患者や腎機能低下例では、6.0~6.4%の段階で早期導入を推奨する場合もあります。
高齢者や低血糖リスクの高い患者では、目標を7.0%前後に緩和し、個別化治療を行うことが重要です。
薬剤選択は、メトホルミンを第一選択とし、必要に応じてSGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬、インスリン療法などを組み合わせる方針が一般的です。 -
質問:糖尿病で一番強い薬は何ですか?回答:血糖降下力の最強クラスはインスリン療法です。
特に持続型インスリン注射やポンプ療法では、絶食時・食後の血糖コントロールを自在に調整でき、重症化例や1型・進行した2型糖尿病で不可欠です。
経口薬では、GLP-1受容体作動薬(セマグルチドなど)が5~15%の体重減少を伴う強力な降下効果を示し、SGLT2阻害薬(ダパグリフロジンなど)も心腎保護効果を持ちつつ3~4%の減量をもたらします。
α-グルコシダーゼ阻害薬やスルホニル尿素薬は比較的緩やかな効果であり、経口薬単独ではインスリンに及びません。 -
質問:内科でもらえる痩せる薬は?回答:日本の病院では、体重を減らす専用の薬は原則としてありません。
代わりに医師は以下を組み合わせてアドバイスします。
* 生活習慣改善:食事量を減らし、運動を増やす
* 漢方薬(防風通聖散など):便通改善やむくみ取りで1~2kg程度の減量をサポート
* 糖尿病薬の応用(自由診療):GLP-1受容体作動薬を使うと5~15%の減量も可能ですが、保険適用外です -
質問:糖尿病で絶対食べてはいけないものは何ですか?回答:「完全にNG」の食べ物はありませんが、血糖値を急に上げやすいものは控えましょう。
* 砂糖たっぷりの清涼飲料水や菓子(ジュース、ケーキ、クッキー)
* 白米や白いパン、うどんなどの精製炭水化物(玄米や全粒粉に置き換えを)
* 果物のジュース(果実より血糖値が上がりやすい)
* 揚げ物・脂っこい食事の過剰摂取(インスリン効きにくくなる)
* カクテルなどの糖質入りアルコール
これらを無理なく減らし、バランス良く食べることが大切です。
オカメット500mgの口コミ・レビュー
-
現在口コミが投稿されていません
口コミやレビューの正当性を保つため、商品をご購入して頂いた方に限り、1商品につき1回の投稿が可能となっております。
サイトにログインをして、ご購入履歴をお確かめのうえ、口コミ投稿をしてください。