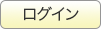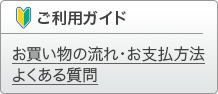ヴィヴス

-
英語表記Vivus.Inc.
-
設立年月日1991年4月4日
-
代表者John Amos
-
国アメリカ合衆国
-
所在地900 E. Hamilton Avenue, Suite 550, Campbell, CA 95008, USA
革新的な医薬品開発で患者の生活を改善するヴィヴス
ヴィヴスは、1991年4月4日に設立された米国のバイオ医薬品企業です。
本社をカリフォルニア州キャンベルに置き、肥満、肥満や勃起不全の治療薬の開発・販売に特化しています。
同社は、患者の生活の質を向上させる革新的な治療法の開発に注力し、臨床開発や商業化の専門知識を活かして、重篤な医学的状態や生命を制限する疾患を持つ患者のニーズに対応することを目指しています。
ヴィヴスの主力製品の一つが、肥満治療薬のQsymiaです。
Qsymiaは、フェンターミンとトピラマートの組み合わせによる処方薬で、食欲抑制と代謝促進の効果があります。
この製品は、適切な食事療法と運動療法と併用することで、肥満患者の体重減少を支援します。
Qsymiaの開発と販売は、増加し続ける肥満問題に対する ヴィヴスの取り組みを示しています。
もう一つの重要な製品は、勃起不全治療薬のSTENDRAです。
STENDRAは、アバナフィルを有効成分とする経口薬で、必要に応じて服用することができます。
この製品は、従来の同種薬に比べて作用の発現が速いという特徴があり、患者のニーズに柔軟に対応できる選択肢となっています。
ヴィヴスは、これらの主力製品を中心に、継続的な研究開発と市場戦略の改善に取り組んでいます。
同社の方針は、既存製品の適応拡大や新規化合物の開発を通じて、製品ポートフォリオを拡充することです。
また、患者や医療提供者のニーズに応えるため、製品の使いやすさや安全性の向上にも注力しています。
ヴィヴスの患者中心のアプローチと科学的イノベーション
ヴィヴスの特筆すべき点は、患者中心のアプローチと科学的イノベーションの追求にあります。
同社は、患者のQOLを向上させることを最優先事項とし、この目標に向けて全ての事業活動を展開しています。
ヴィヴスは、患者や医療提供者との緊密な対話を通じて、未満たされた医療ニーズを特定し、それらに対応する革新的な治療法の開発に取り組んでいます。
例えば、Qsymiaの開発過程では、肥満患者が直面する日常的な課題や、既存の治療法の限界について詳細な調査を行いました。
その結果、単なる体重減少だけでなく、長期的な体重管理と関連する健康リスクの低減を可能にする製品の必要性が明らかになりました。
ヴィヴスは、これに基づいてQsymiaを設計し、臨床試験を通じてその有効性と安全性を実証しました。
ヴィヴスの研究開発チームは、最新の科学的知見と技術を活用し、継続的にイノベーションを追求しています。
同社は、代謝疾患や心血管疾患の分子メカニズムに関する理解を深め、より効果的で副作用の少ない治療法の開発を目指しています。
また、デジタルヘルステクノロジーの活用にも積極的で、患者のアドヒアランス向上や治療効果のモニタリングを支援するアプリケーションの開発にも取り組んでいます。
ヴィヴスは、製品開発だけでなく、市販後の安全性モニタリングと製品改良にも力を入れています。
患者や医療提供者からのフィードバックを積極的に収集し、製品の改善や新たな適応症の探索に活かしています。
この継続的な改善プロセスにより、ヴィヴスの製品は常に進化し、患者のニーズに応え続けることができています。
ヴィヴスのグローバル展開と市場戦略
ヴィヴスは、米国を拠点としながらも、グローバルな視点で事業展開を行っています。
同社の製品は、世界中の患者に届けられることを目指して開発されており、各国の規制当局との緊密な協力のもと、承認取得と市場導入を進めています。
Qsymiaは、FDAの承認を受けて米国市場で販売されています。
現在も各国の肥満治療ガイドラインや医療制度の違いを考慮しながら、Qsymiaの有効性と安全性を示すデータを提示し、規制当局との対話を重ねています。
STENDRAについても、米国市場での展開に加え、欧州ではSpedraの商品名で販売されています。
ヴィヴスは、各地域のパートナー企業と提携し、現地の医療ニーズや市場特性に合わせたマーケティング戦略を展開しています。
例えば、欧州では、STENDRAの即効性を強調したプロモーションを行い、競合製品との差別化を図っています。
ヴィヴスの市場戦略の特徴は、単なる製品販売にとどまらず、包括的な疾患管理プログラムの提供を目指している点です。
例えば、Qsymiaの処方と併せて、オンラインリソースやサポートなどを提供することで、患者の長期的な治療成功率の向上を図っています。
引用 : https://www.vivus.com/about-vivus/
引用 : https://www.vivus.com/products/
引用 : https://qsymia.com/
引用 : https://qsymia.com/savings-support
引用 : https://stendra.com/
よくあるご質問(FAQ)
-
質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:
薬が手に入らない理由はいくつかあります。
主に、薬の開発には多くの時間と資金が必要で、これに伴うリスクが高いため、企業が開発を選ばないことがあります。
また、法的な規制や承認手続きも複雑で、これに対応するための専門知識とリソースが必要です。
これらの要因が重なり、薬の供給が難しくなることがあります。 -
質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:
薬の供給不足は、いくつかの理由で起こる可能性があります。
例えば、原料が手に入らない、製造設備にトラブルがあるなどの製造面での問題や、輸送中の事故や天候不良といった流通面での問題があります。
また、薬の需要が急増することでも供給が追い付かなくなることがあります。
製薬会社は供給を安定させるために様々な対策をしていますが、それでも一時的に供給不足が発生する可能性はあります。 -
質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:
薬は処方箋なしではもらえないのは、医師が患者さんの病状を診断して最適な薬を決めるためです。
処方箋にはその薬の詳細が書かれており、薬剤師はそれに基づいて調剤します。
また、薬の飲み合わせや重複投薬を防ぐためにも、医師や薬剤師が患者さんの薬の情報を把握することが重要です。
これらの理由で、薬は医師の診断と指導のもとで使う必要があり、処方箋が求められます。 -
質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:
残薬は医療費の無駄使いとなり、患者さんの治療にも悪影響を及ぼす社会問題です。
薬の種類や量が変わると、患者さんは自宅に同じ薬があることに気づかず、無駄に残薬が増えることがあります。
また、残薬は患者さんの服薬管理が不十分であることも示します。
この問題を解決するためには、薬剤師と患者さんのコミュニケーションを良好にし、適切な服薬指導を行うことが重要です。
また、残薬を再利用するシステムの導入も検討されています。
これらの取り組みで、残薬問題の改善が期待されています。 -
質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:
残薬がある場合は、医師に伝えることが推奨されています。
残薬を伝えることで、医師は患者さんの症状に合わせた適切な治療を提案できます。
残薬を隠したり無断で服薬を中止すると、次の処方が不適切になる可能性があります。
そのため、残薬があれば遠慮せずに医師に伝えることが大切です。
これにより、医師との信頼関係を築き、適切な服薬指導を受けることができます。 -
質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:
薬剤師が薬について尋ねるのは、患者さんの健康を守り、最適な治療を提供するためです。
患者さんが使っている薬の種類や量、副作用、飲み合わせなどを把握することで、薬の安全性と効果を高めます。
また、薬剤師は患者さんのアレルギーや過去の薬の反応、健康状態を考慮し、個々に合った治療を提案します。
これらの情報は、患者さんの健康と安全を保つために重要です。 -
質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:
薬局で残った薬を再びもらうことは通常できません。
処方された薬は患者さん個人のためのもので、他の人に譲ることは法律で禁止されています。
余った薬がある場合は、薬局に持参して薬剤師に相談するのが適切です。
薬剤師は残薬の確認を行い、次回の処方に反映させたり、適切な処分方法を教えてくれます。
残薬を医師に報告し、適切に処分することは環境保護のためにも重要です。 -
質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:
病院で処方された薬を一包化することは可能です。
一包化とは、服用のタイミングが同じ薬を一回分ずつまとめる方法で、服用管理が容易になります。
医師の指示があれば、一包化は行われますが、指示がなくても実費で対応してくれる薬局が多いです。
ただし、吸湿性の高い薬や特殊な管理が必要な薬は、一包化ができない場合がありますので、薬剤師に相談することが大切です。
また、一包化された薬は、通常の包装よりも使用期限が短くなることがあるため、依頼する前に薬剤師に確認することをおすすめします。 -
質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:
病院で処方された薬が余った場合は、まず薬局に持参し、余った薬の種類や量を伝えましょう。
薬剤師が状況を確認し、次回の処方で適切な量になるよう医師に連絡を入れてくれます。
さらに、次回の診察時に減量について相談できるように、薬剤師がメモを作成してくれることもあります。
ただし、薬の種類や量を具体的に伝えないと、適切な対応が難しくなります。
正確な情報を提供することが大切です。 -
質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:
薬の説明書は、安全で効果的に薬を使用するために重要な情報が含まれています。
使用方法や副作用、保存方法などが記載されているため、説明書を理解し、必要な情報を把握した上で保管することが推奨されます。
説明書を捨てるかどうかは、将来再確認する可能性や、家族が使う可能性を考慮して判断してください。
必要に応じて参照できるようにしておくと安心です。 -
質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:
置き薬は、家庭や学校、企業に基本的な薬を常備するサービスで、特に医療アクセスが難しい場所で役立ちます。
健康状態に応じて必要ない場合もありますが、置き薬があると、いざという時にすぐ対応できる安心感が得られます。
必要に応じて使うことが推奨されています。 -
質問:薬は何年くらい持つ?回答:
薬の保存期間は、未開封の状態で一般的に3~5年ですが、薬の種類や保存状態によって異なることがあります。
薬は、適切な温度と湿度で直射日光を避けて保管するのが推奨されます。
開封後の保存期間は薬の種類によりますが、一般的には約半年です。
これらを考慮して、薬の保存には注意が必要です。 -
質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:
病院でもらった薬の寿命は、薬の種類や保管状態によって異なりますが、一般の薬と同様に「使用期限」や「有効期限」が設定されています。
これは、薬が最も効果的で安全な状態である期間を示しています。
有効期限を過ぎた薬は、効果が低下する可能性があるため、使用しない方が良いでしょう。 -
質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:
薬を冷蔵庫に保管することは一般的に推奨されません。
冷蔵庫の低温や温度差で結露が生じると、薬の品質が低下する可能性があります。
また、一部の薬品では冷蔵庫で結晶ができることもあります。
基本的には、薬は直射日光を避けた涼しい場所で保管するのが最良です。
ただし、冷蔵庫で保管が必要な薬もあるため、その場合は医師や薬剤師に確認してください。 -
質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:
2022年9月30日から、薬局以外の場所でもオンラインで薬の服薬指導が可能になりました。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
・薬剤師は薬局に所属していること
・患者の健康状態に関する情報を得られる体制が整っていること
・第三者が入れない安全な場所で行うこと
・騒音やネットワークの問題がない場所で行うこと
これらの条件を守れば、薬局以外の場所でもオンライン服薬指導が受けられます。 -
質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:
オンラインで薬の服薬指導を受けることが可能です。
これは、パソコンやスマートフォンを使って行うもので、法令改正により実施が認められました。
ただし、オンライン服薬指導を行う際は、その特性を理解し、適切な体制を整えることが必要です。
患者さんの個別の状況に応じて、薬剤師が適切な対応をすることが求められます。 -
質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:
処方箋なしで購入できる薬は「一般用医薬品」または「OTC(OverTheCounter)医薬品」と呼ばれます。
これらは薬局やドラッグストアで直接買えます。
一般用医薬品は、日常的に起こりやすい症状に対応するもので、医師の診察なしに自己判断で使うことができます。
ただし、「要指導医薬品」と呼ばれる一部の薬は、薬剤師からのみ購入できます。 -
質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:
以前は、薬のオンライン服薬指導が電話だけでも可能でしたが、これは新型コロナウイルス感染症対策として一時的に導入された「0410対応」と呼ばれる措置です。
現在は、基本的に映像と音声を使ったオンライン服薬指導が求められています。
電話のみでの指導は、薬剤師が十分な説明を行うことが条件となっています。
この制度は新型コロナウイルスの収束までの一時的なもので、今後は映像と音声による対応が必須となります。
そのため、状況によっては電話だけでの指導が可能かどうかが変わる可能性があります。 -
質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:
オンラインで薬を受け取る方法は以下の通りです。
1.医療機関で診察を受け、オンライン服薬指導を希望すると伝えます。
2.医療機関からオンライン服薬指導の申込み用のSMSが送られてきます。
3.SMSに記載されたURLをタップして指定されたサイトにアクセスします。
4.サイトで「自宅で受け取る」を選択します。
5.予約の日時に、指定された通信手段(例:ビデオ通話)で薬剤師と繋がります。
6.その後、服薬指導を受けます。
7.服薬指導が終わったら、指定された方法(例:クレジットカード)で料金を支払います。
8.最後に、調剤された薬が自宅に配送されます。
配送は品質を保つよう専門業者が行うことが多いです。 -
質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:
オンラインでの薬の服薬指導を受けている人は全体の約6.1%です。
この数字には、電話など画像のない方法も含まれています。
また、オンライン診療を利用した人の約8割が再利用したいと考えており、未経験者よりも高い割合です。
このため、オンラインサービスの普及と啓発が期待されています。