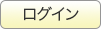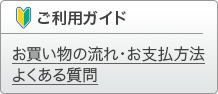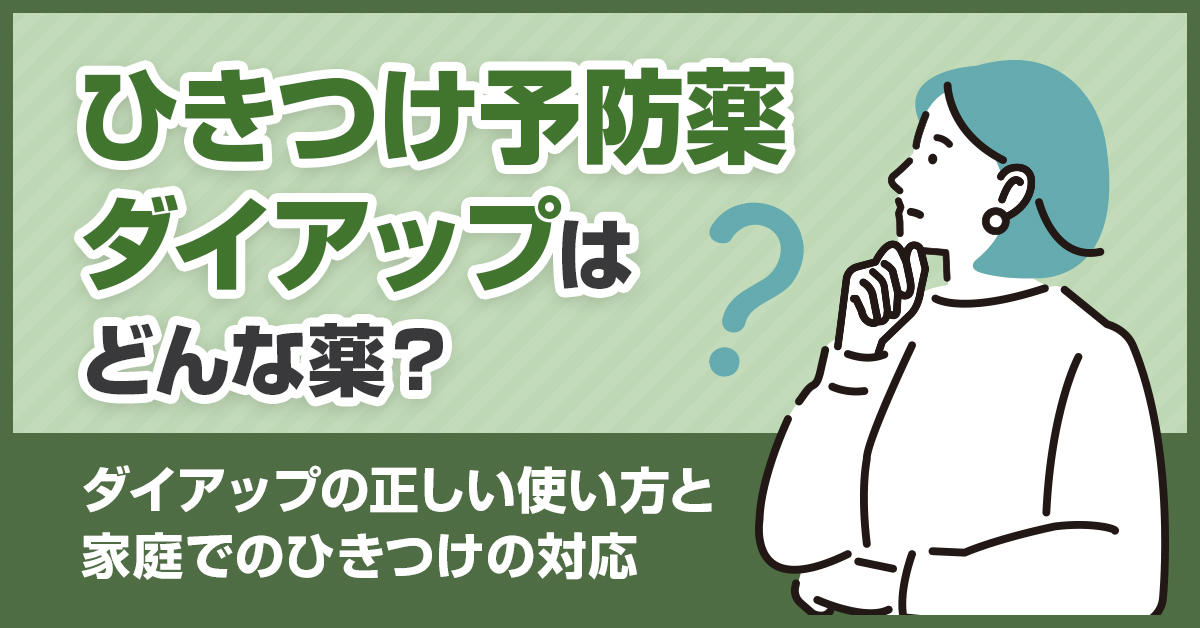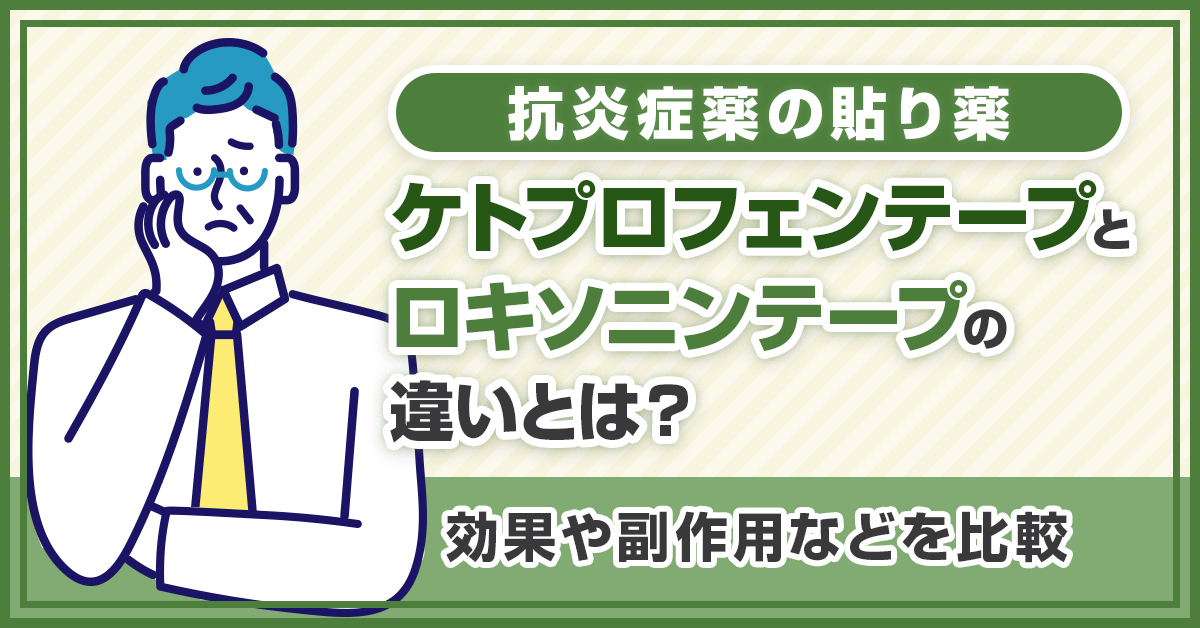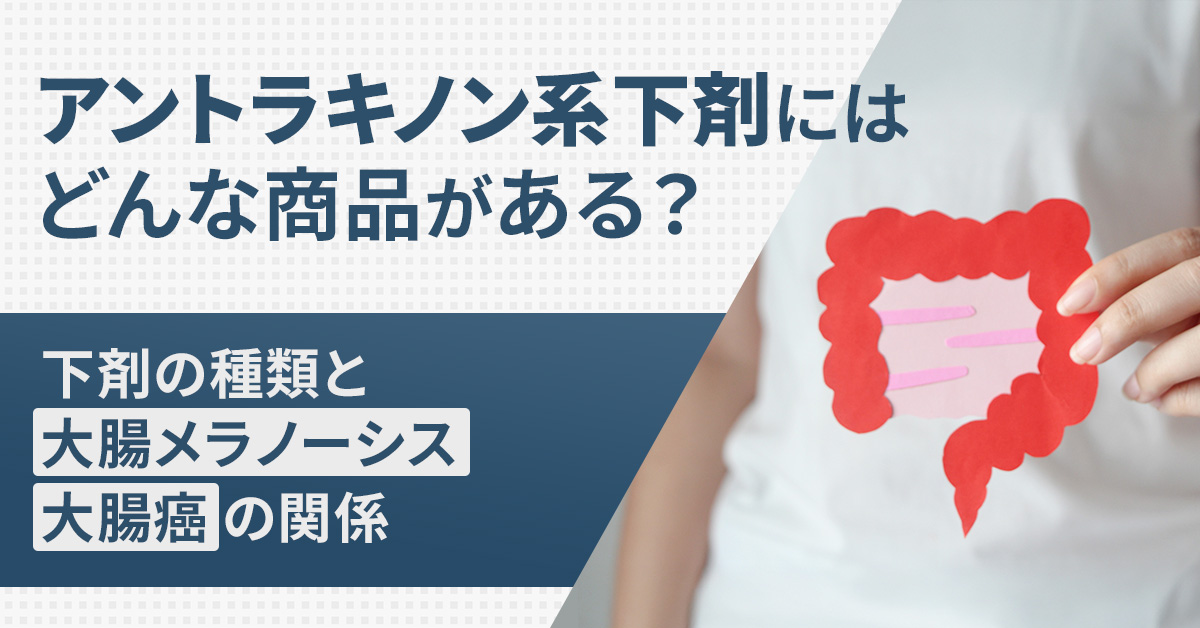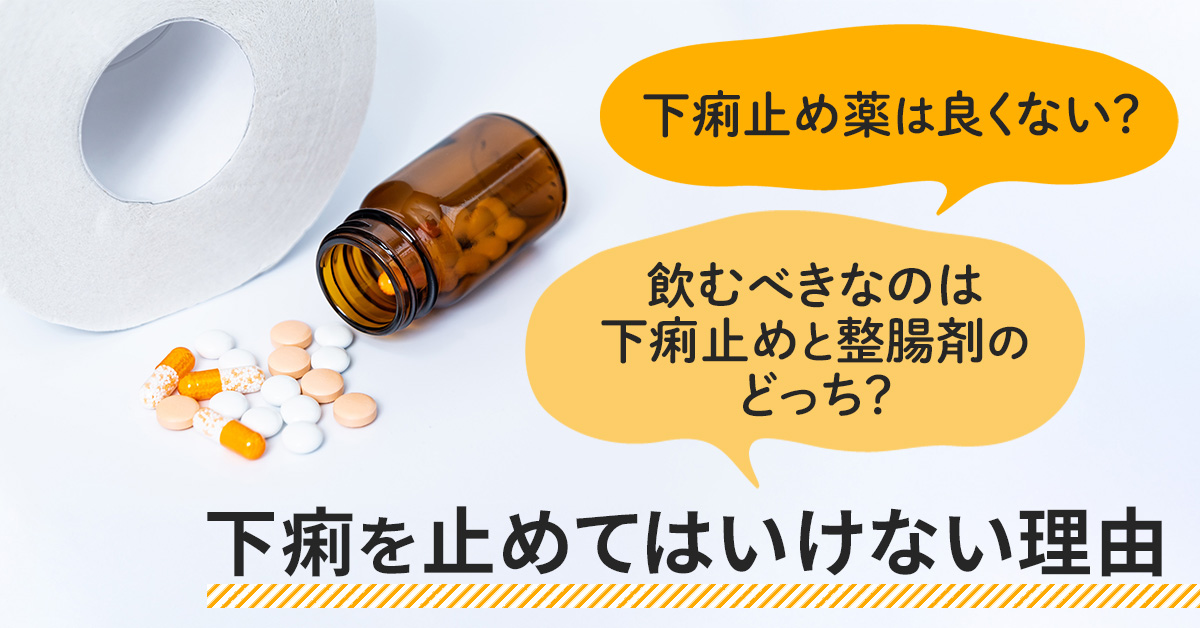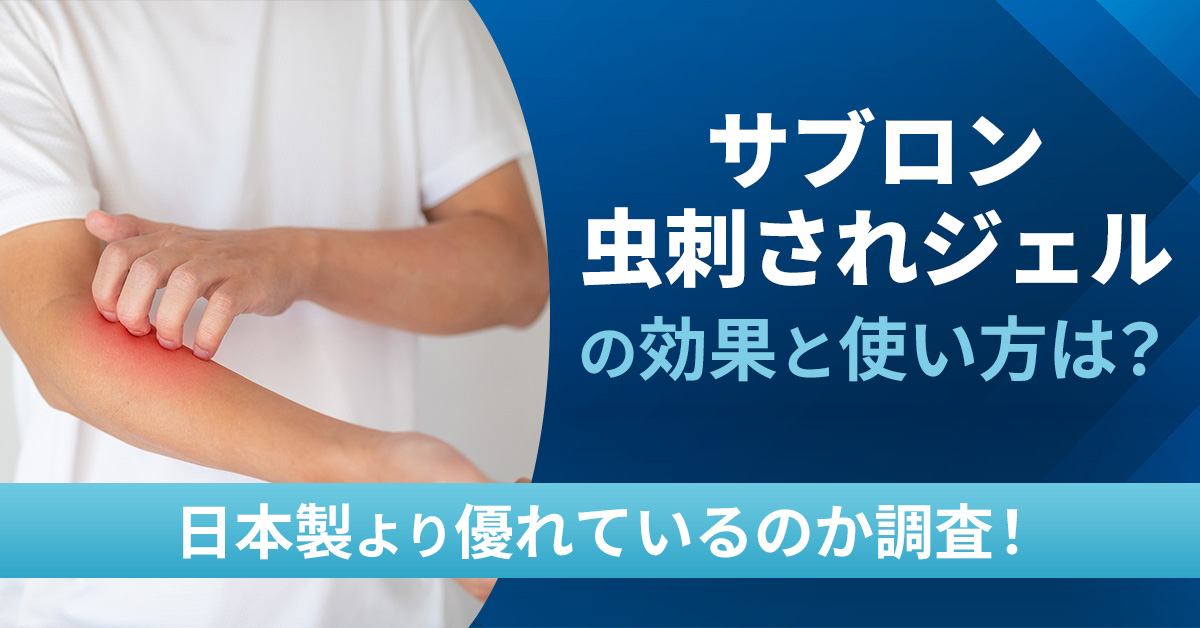筋緊張緩和薬はその名前の通り、筋肉からの緊張の伝達を抑えて筋弛緩作用を示す薬剤であり、なかでも使用されることの多い薬剤がミオナールです。
今回はミオナールを正しく使うために知っておきたい効果や副作用を紹介します。
また、よく疑問としてあがるミオナールとロキソニンといった他の薬剤との飲み合わせについても解説していきます。
筋緊張緩和薬を安全に使用するためにも、しっかり内容を理解しておきましょう。
筋緊張緩和薬ミオナールとは
筋緊張緩和薬ミオナールは有効成分エペリゾン塩酸塩を含む薬剤の先発薬で、ミオナール顆粒10%とミオナール錠50mgの2種類がエーザイから販売されています。
また、後発品として日医工や東和薬品など複数の製薬会社からエペリゾン塩酸塩錠50mgが販売されています。
つまり、ミオナールとエペリゾンは名前こそ異なりますが、同じ成分が配合された同じ効果が得られる薬ということです。
ここではミオナールを中心に、その効果や飲み合わせなどについて解説していきます。
ミオナールの効果
筋緊張緩和薬のミオナールには主に2種類の作用があるとされています。
1つは骨格筋の緊張を緩和させる作用です。
脳から脊髄を通って指令を出すことで筋肉が緊張しますが、この指令が過剰になりすぎると筋肉が凝り固まり、肩こりや腰痛、頭痛などを引き起こします。
ミオナールはこの脳や脊髄から伝わる筋肉への指令を抑え、筋肉の緊張を和らげる作用があります。
2つめは血管を拡張させて血流を増やす作用です。
筋肉が緊張して血流が悪化すると、疲労物質が蓄積したり、神経がダメージを受けて痛みや痺れを引き起こしたりすることがあります。
血管拡張作用のあるミオナールを使用し血流を改善することで、疲労物質を排除して身体の隅々にまで栄養を送り届けられるようになります。
このような作用を持つミオナールは、肩こりや頭痛、腰痛、頸部痛、手足のこわばりなどの筋緊張にともなう症状を改善することから、肩関節周囲炎や頸肩腕症候群、腰痛症、痙性麻痺などの治療に使用されます。
ただし、ミオナールには血流を改善する効果はあるものの、うつ病に対しての効果は認められていません。
ミオナールの用法用量
ミオナールは通常成人にはエペリゾン塩酸塩に換算して1日150mgを、つまりミオナール錠50mgであれば1回1錠を1日3回食後に服用するのが基本ですが、用量は年齢や症状によって適宜増減されます。
また、嚥下機能が低下している場合には、服用しやすいミオナール顆粒10%が選択できるのも、この薬剤のメリットと言えるでしょう。
ミオナールの副作用
ミオナールの主な副作用として発疹やかゆみといった皮膚症状、吐き気や腹痛、食欲不振といった消化器症状、めまいやふらつき、脱力感といった精神神経症状が現れることがあります。
特に発赤や蕁麻疹、呼吸困難などはアナフィラキシーの初期症状、発熱や水疱、眼の充血などは中毒性表皮壊死融解症と皮膚粘膜眼症候群などの初期症状の可能性があるため、症状が現れた時にはすぐに医療機関を受診するようにしてください。
ミオナールの禁忌・飲み合わせ
ミオナールは過敏症の方や妊婦の使用が禁忌であるのに加え、肝障害を抱えている方や授乳婦、新生児~小児は注意して使用する必要があります。
また、類似成分のトルペリゾン塩酸塩が配合されているメトカルバモールは眼の調節障害を引き起こす恐れがあるため、飲み合わせに注意が必要です。
一方、ミオナールと一緒に処方されることの多いロキソニンは筋肉の痛みに作用する薬であり、特に飲み合わせに関する注意はありません。
ミオナール以外の筋緊張緩和薬
ミオナール以外にもテルネリン、リンラキサー、ダントリウムといった筋緊張緩和薬が発売されており、その特徴は少しずつ異なります。
強さの順位に関するデータがありませんが、最も処方されている筋緊張緩和薬はミオナールを含むエペリゾン塩酸塩で、次いでテルネリンを含むチザニジン塩酸塩、ギャバロンとリオレサールを含むバクロフェンと言われています。
ここではミオナール以外の筋緊張緩和薬をいくつか紹介していきます。
チザニジン塩酸塩
有効成分チザニジン塩酸塩を含む筋緊張緩和薬の先発薬は、サンファーマのテルネリン顆粒0.2%とテルネリン錠1mgです。
後発品として協和薬品工業や鶴原製薬などから、チザニジン錠1mgが販売されています。
チザニジン塩酸塩はアドレナリン受容体であるa2受容体に作用して筋緊張緩和作用を示す薬剤で、頸肩腕症候群や腰痛、痙性麻痺などの治療に使われます。
眠気や口渇、倦怠感などの精神神経症状、吐き気や食欲不振、腹痛といった副作用が起こることがあり、特にめまいや脱力感、立ちくらみといった症状が現れた時には重篤な副作用である急激な血圧低下が考えられます。
他にもショックや心不全、呼吸障害、肝障害などの報告もあるため、体調の変化に気づいた時にはすぐに医療機関を受診してください。
また、このような副作用があるため、過敏症、重篤な肝機能障害がある方、妊婦は禁忌です。
飲み合わせに関しても、フルボキサミンやシプロフロキサシンとの併用は禁止されています。
バクロフェン
有効成分バクロフェンを含む筋緊張緩和薬の先発薬は、第一三共のギャバロン髄注0.005%、ギャバロン髄注0.05%、ギャバロン髄注0.2%です。
後発品にはアルフレッサファーマのギャバロン錠5mgとギャバロン錠10mg、サンファーマのリオレサール錠5mgとリオレサール錠10mgがあります。
ギャバロン髄注を脊髄の周囲へ直接投与するバクロフェン髄注療法は、痙縮の症状が重い患者さんに対する効果が飲み薬よりも高いのが特徴で、固くなった下肢の筋肉を柔らかくしたり、筋肉の痙攣を抑えたりする効果が期待できます。
ただし、バクロフェン髄注療法を行うためにはポンプやカテーテルを身体に埋め込む手術を行う必要があります。
バクロフェンの主な副作用には頭痛や眠気、しびれ、痙攣発作、歩行困難などがあり、重大な副作用として幻覚や錯乱などの報告もあります。
また、バクロフェンは離脱症状も確認されているので薬剤を勝手に中断しないようにしてください。
使用上の注意として過敏症や妊娠中の方は禁忌、血圧降下剤や中枢抑制剤をはじめとする複数の薬剤で作用に対する影響が報告されています。
さらにアルコールとの飲み合わせにも注意が必要です。
クロルフェネシンカルバミン酸エステル
有効成分クロルフェネシンカルバミン酸エステルを含む筋緊張緩和薬の先発薬は、大正製薬のリンラキサー錠125mgとリンラキサー錠250mgです。
後発品には沢井製薬と鶴原製薬から、クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mgとクロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mgが発売されています。
クロルフェネシンカルバミン酸エステルは椎間板ヘルニアや変形性脊椎症といった運動器の疾患による痛みを伴う痙縮の治療に使用します。
めまいやふらつき、眠気など精神神経症状や胃痛や胸やけといった消化器症状の副作用が現れる恐れがあることに加え、ショックや中毒性表皮壊死症などの重篤な副作用を引き起こす可能性もあります。
このようなことから、過敏症や肝障害を抱えている方、妊婦は使用禁止、フェノチアジン系薬剤や塩酸クロルプロマジンなどで互いに作用を強める恐れがあるため、併用には注意が必要です。
また、アルコールも薬剤に影響を与えるため、控えるようにしてください。
ダントロレンナトリウム水和物
有効成分ダントロレンナトリウム水和物を含有する筋緊張緩和薬の先発薬はオーファンパシフィックのダントリウム静注用20mgとダントリウムカプセル25mgの2つで、後発品はありません。
ダントロレンナトリウム水和物は骨格筋の興奮や収縮などを抑えて筋肉の緊張を緩和させる作用がある薬剤です。
痙性麻痺に加えて、こむら返りや悪性症候群などの治療に使用されることもあります。
しかしながら、ダントロレンナトリウム水和物の主な副作用には脱力感や全身倦怠感、発疹、かゆみ、光線過敏症などがあり、重篤な副作用としてアナフィラキシーや肝障害、PIE症候群、胸膜炎、イレウスの報告があります。
そのため、使用中に体調の変化を感じた時には速やかに医療機関を受診するようにしましょう。
また、ダントロレンナトリウム水和物は過敏症、肝疾患、筋無力症、心疾患や閉塞性肺疾患による心肺機能が低下している方、妊婦の使用は禁止です。
卵胞ホルモン剤との併用では重篤な肝障害を引き起こす可能性があるため、注意が必要とされています。
筋緊張緩和薬ミオナールは筋肉の緊張を緩和する薬
筋緊張緩和薬ミオナールは筋肉の緊張を緩和して血流を改善させる作用があるため、肩関節周囲炎や頸肩腕症候群、腰痛症、痙性麻痺などの治療に使用されます。
ミオナールの主な副作用として、かゆみなどの皮膚症状や吐き気といった消化器症状、めまいなどの精神神経症状が現れることがあるため、過敏症や妊婦の使用は禁止されています。
ただし、飲み合わせに関してはメトカルバモールが併用注意とされているだけなので、鎮痛剤のロキソニンとの飲み合わせに関しては特に注意書きはありません。
ミオナール以外にも、テルネリンやギャバロンなどの筋緊張緩和薬があり、後発品も含めると非常に多くの製品が処方薬として販売されています。
それぞれ成分によって特徴が異なるため、使用する際は用法用量をよく確認するようにしてください。