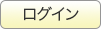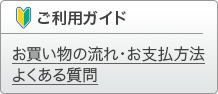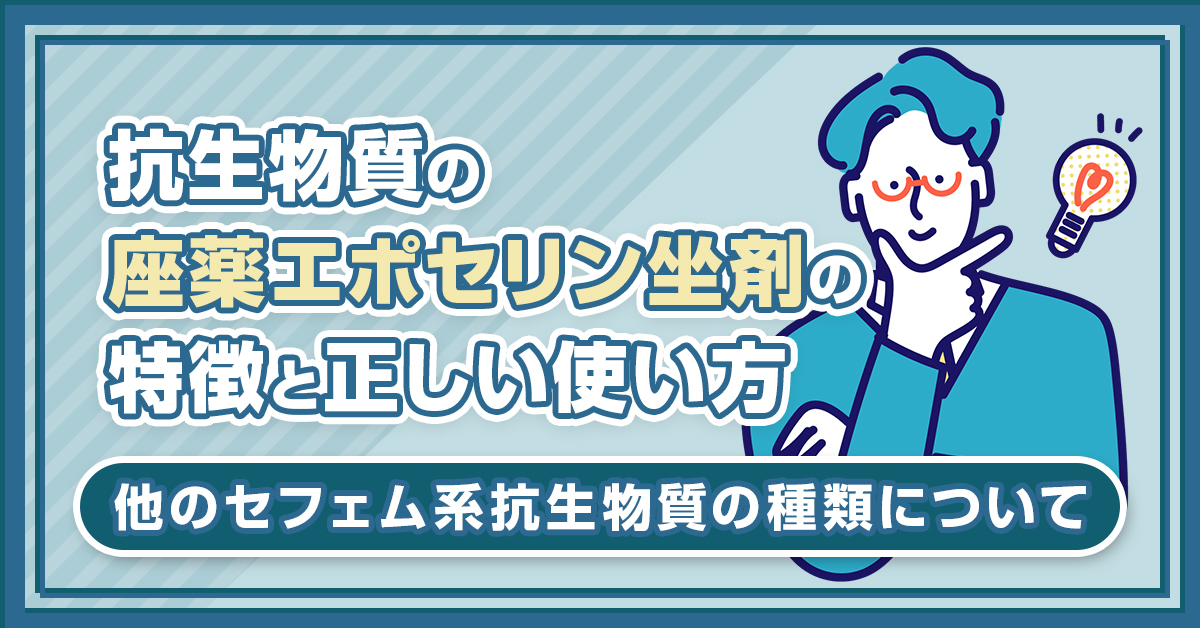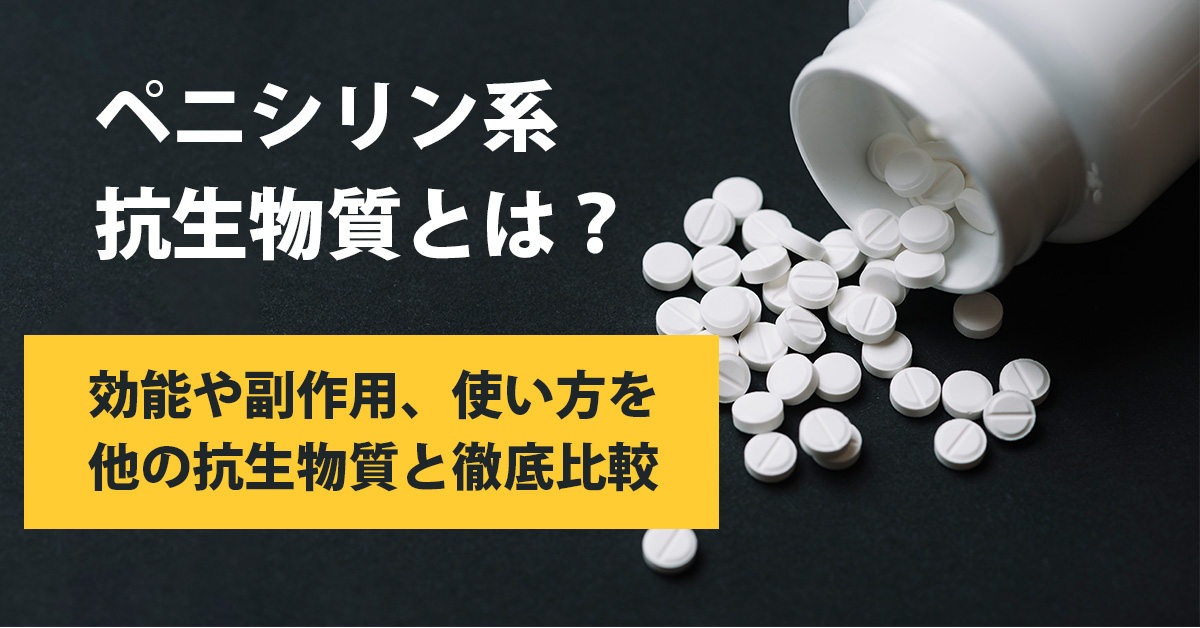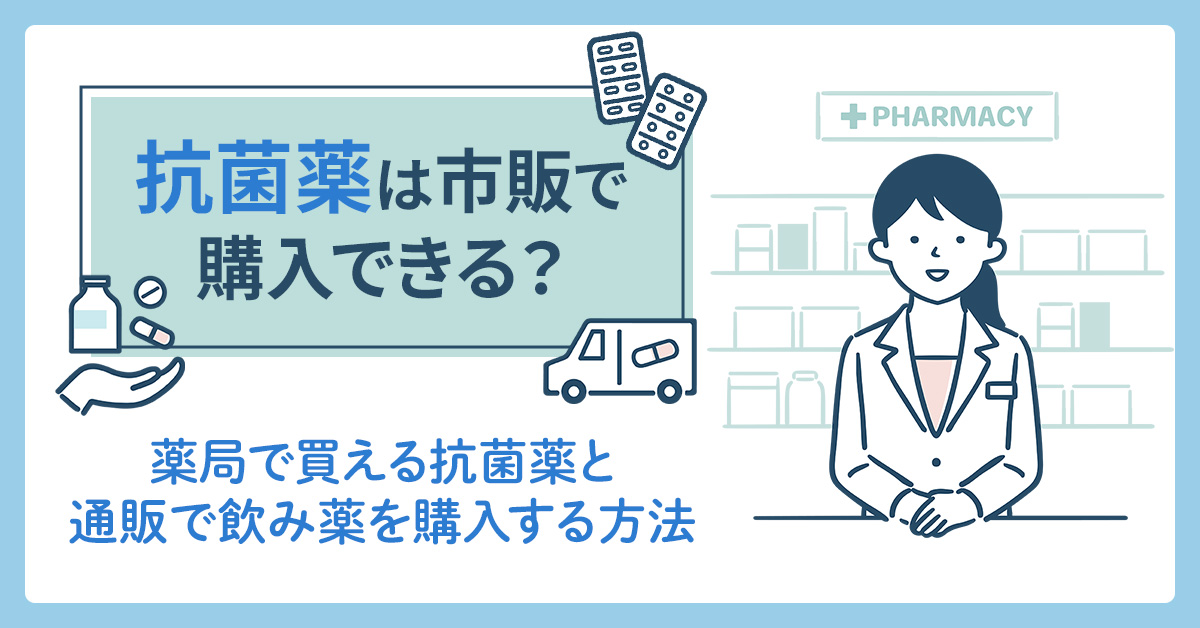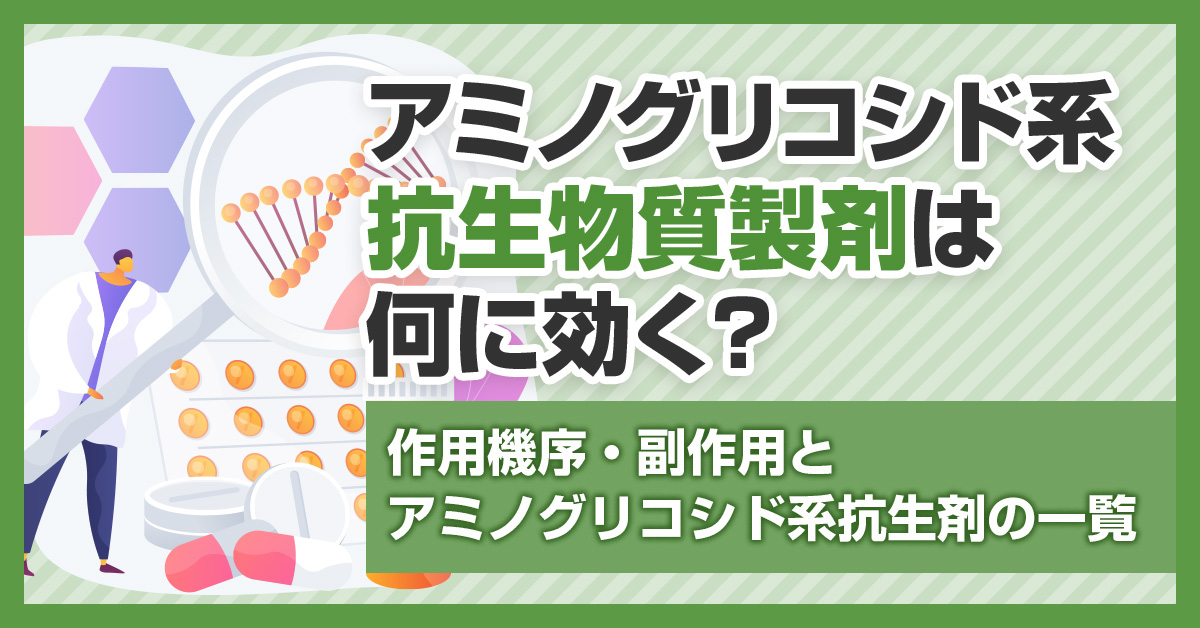細菌感染に効果を示す抗生物質は飲み薬だけでなく、座薬もあるのはご存知でしょうか。
あまり知られていないので、抗生物質の座薬の存在を知らずに処方されて、慌ててしまう方も少なくないのかもしれません。
ここでは抗生物質の座薬であるエポセリン坐剤の効果や副作用に加え、座薬の正しい使い方を解説していきます。
抗生物質について疑問がある方、座薬の使い方に困っている方はぜひ参考にしてください。
抗生物質の座薬とは
座薬は肛門から体内に挿入し、体温によって溶かして直腸で成分を吸収する剤型の薬剤で、子どもや嚥下機能の問題で薬剤を飲むことが難しい場合に使用されます。
一般的には座薬と内服薬の間では効果の差はないとされていますが、座薬は食事や消化酵素の影響を受けにくかったり、肝臓によって薬剤が分解されなかったりする特徴があり、安定した効果を発揮しやすいとも言われています。
ここでは抗生物質の座薬の有効成分セフチゾキシムナトリウムが配合されたエポセリン坐剤の効果や副作用について紹介していきます。
エポセリン坐剤の効果
セフチゾキシムナトリウムが主成分のエポセリン坐剤はセフェム系の第3世代の抗生物質であり、細菌の細胞壁の合成を阻害する作用を持っています。
細胞壁を持つ細菌に対し、細胞壁合成に必要となるペニシリン結合タンパク質に作用して細胞壁の合成を阻害することにより抗菌作用を発揮します。
抗生物質は世代ごと・成分ごとに得意とする細菌の種類が異なり、セフェム系第3世代に属するエポセリン坐剤は、次のような菌種に適応しています。
【エポセリン坐剤の適応菌種】
- レンサ球菌属
- 肺炎球菌
- 大腸菌
- クレブシエラ属
- エンテロバクター属
- シトロバクター属
- プロテウス属
- セラチア属
- プロビデンシア属
- インフルエンザ菌
- モルガネラ・モルガニー
- ペプトストレプトコッカス属
- プレボテラ・メラニノジェニカ
- バクテロイデス属
これらの細菌に適応があることから、急性気管支炎や肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、腎盂腎炎、膀胱炎などの治療に使われます。
ただし、エポセリン坐剤は抗菌作用を持つ抗生物質なので、直接的に熱を下げる効果はありません。
エポセリン坐剤の用法用量
エポセリン坐剤はセフチゾキシムナトリウムが主成分の先発薬で、製品はエポセリン坐剤125とエポセリン坐剤250の2種類が長生堂製薬から販売されています。
エポセリン坐剤は小児に使用する薬剤で、通常、体重kgあたりにセフチゾキシムナトリウムとして1日20~70mgを3~4回に分けて肛門に挿入しますが、年齢や症状によって量が増減することもあります。
抗生物質の座薬の使用タイミングについては医師の指示に従って使うようにしてください。
エポセリン坐剤の副作用
エポセリン坐剤でよく見られる副作用は下痢です。
抗生物質は人間の身体に悪さをする菌だけではなく、良い影響を与える菌にも抗菌作用を示すため、座薬の使用によって腸内細菌のバランスが崩れて便が緩くなることがあります。
他にも、発疹やかゆみなどの皮膚症状が現れることがあります。
軽い皮膚症状であればそれほど心配は要りませんが、ひどい蕁麻疹が起きたり発熱を伴ったり、息苦しさを感じたりするような時にはアナフィラキシーショックの可能性があるので、すぐに医療機関を受診してください。
また、エポセリン坐剤には肝障害や急性腎不全、大腸炎、重い血液の症状などの重篤な副作用の報告もあります。
これらの副作用が起きる可能性はごく稀とされていますが、体調の変化に留意して見逃すことのないように気を付けて使用していきましょう。
エポセリン坐剤の禁忌・飲み合わせ
エポセリン坐剤やセフェム系抗生物質で蕁麻疹などのアレルギーを発症したことがある方、妊娠中の方は使用禁止です。
また、アレルギー体質や気管支喘息、重度の腎障害を抱える方は副作用が出やすいために注意して使用する必要があります。
飲み合わせに関しては血栓の予防薬であるワルファリンカリウムは作用増強、尿の排出を促す利尿薬とフロセミドは腎障害の悪化のリスクが上がるため、併用には注意が必要です。
副作用を避けるためにも、他の薬剤と併用する必要がある時には医師や薬剤師に相談しましょう。
抗生物質の座薬の正しい使い方
セフェム系抗生物質のエポセリン坐剤は肛門に挿入して使用する薬剤です。
しかしながら、使い方を誤ると十分な効果が得られないばかりか、思わぬ副作用を招いてしまう恐れもあります。
そこで、ここでは子どもに対して使用する場合の正しい座薬の使用方法をお伝えしていきます。
座薬の挿入手順は次の通りです。
- 薬剤を触る人は手を洗って清潔にしておく
- 患者さんの衣服を下してお尻を出す
- 包装から座薬を取り出して先の尖った方から肛門に挿入する
- 座薬が見えなくなるくらい入れたらティッシュなどで1~2分押さえて戻らないようにする
- 5分後くらいに肛門を再度確認して薬剤が出てきていたらもう一度押し込む
子どもが不安を感じて力を入れると、座薬が出てきてしまうことがあります。
座薬が体内に入らなければ薬剤の効果は得られないので、うまくできないような時には次のワンポイントアドバイスを参考にしてください。
座薬を使用する時のワンポイントアドバイス
座薬の使用が初めてだったり、うまくできなかったりした時にはこちらの内容を確認して対応していきましょう。
座薬を挿入しやすい体勢にする
子どもを座薬が入りやすいような体勢にすることで、挿入しやすく戻りにくくなります。
赤ちゃんであれば、おむつ替えの体勢にすると挿入しやすいので、仰向け寝かせて両手で赤ちゃんの足を持ち上げてみてください。
幼児くらいの子どもであれば、横向きに寝かせて膝を曲げさせると座薬が入れやすいでしょう。
座薬を入れる前にトイレを済ませる
座薬は肛門から直腸に入れる薬剤であるため、挿入後に排便をすると薬剤が体外に排出されてしまいます。
このようなトラブルを避けるためにも、座薬を挿入する前にはトイレを済ませておくことが大切です。
また、もし座薬が出てきてしまっても、新しい座薬を入れ直すのはやめてください。
座薬は溶けるスピードも速く、入れてから10分ほどであっても多くの成分が吸収されているケースもあるからです。
出てきた薬剤を再度入れられるのであれば問題ありませんが、それが難しい時には次の薬の時間まで待つようにしましょう。
数分間室温に戻してから使用する
座薬は溶けやすいことから冷蔵庫で保管するのが一般的ですが、冷たいまま使用すると刺激が強かったり、滑りにくくて入りにくかったりします。
このような時には使用前に数分間おいて室温に戻したり、手で温めたりして使用したりするとよいでしょう。
ただし、夏場の気温が高い時期や暖房器具の近くでは溶けすぎてしまうことがあるので、注意してください。
2種類の座薬は時間を空けて
症状によっては2種類の座薬を処方されるケースがありますが、同時に使用すると薬の吸収率を下げてしまうことがあります。
そのため、1つの座薬を使用した後は30分以上時間を空けてから、次の薬剤を使用してください。
使用する順番については、基本的には医師の指示の通りに、特に指示がない時には症状を早く改善させたい方の薬剤を先に使用します。
エポセリン坐剤以外のセフェム系抗生物質
セフェム系の抗生物質にはエポセリン坐剤以外にも様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。
ここではセフェム系の抗生物質をいくつか紹介していきます。
第1世代
第1世代のセフェム系抗生物質のケフラールやケフレックスは、黄色ブドウ球菌や大腸菌、連鎖球菌に効果があるため、とびひなどの皮膚感染症や基礎疾患のない尿路感染症の治療に使用されます。
第2世代
第2世代のセフェム系抗生物質のセフメタゾールやセフォチアムは、第1世代よりもグラム陰性桿菌への抗菌力を高めた薬剤です。
そのため、中等度までの肺炎や尿路感染症、胆道感染症の治療に使用されています。
第3世代
第3世代のセフェム系抗生物質は入院するような重症感染症である髄膜炎などで効果を発揮するロセフィンやセフォタックスなどの注射薬があります。
この他にセフゾンやメイアクトといった中耳炎や副鼻腔炎、咽頭炎を始めとする多くの感染症の治療で使用されている内服薬も第3世代のセフェム系抗生物質です。
第3世代のセフェム系内服薬は様々な病気で使用されるために耐性菌の問題が取りざたされている薬剤でもあるため、注意して使用する必要があります。
なお、今回中心となっているエポセリン坐剤も第3世代に属しています。
第4世代
第4世代のセフェム系抗生物質のセフェピムはブドウ球菌や連鎖球菌、肺炎球菌などの幅広い細菌に適応があります。
緑膿菌や発熱性好中球減少症にも有効とされています。
第5世代
第5世代のセフェム系抗生物質のザバクサはセフトロザン硫酸塩にβラクタマーゼ阻害薬を配合した薬剤で、緑膿菌やレンサ球菌などに適応があります。
カルバペネム系を避けたい場合に使用されるケースが多い薬剤です。
抗生物質の座薬は正しく使用しよう
抗生物質の座薬であるエポセリン坐剤は第3世代のセフェム系抗生物質に属する薬剤で、急性気管支炎や肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、腎盂腎炎、膀胱炎などの治療に使われています。
抗菌作用を持つ薬剤であるため、腸内環境のバランスが崩れることによる下痢や発疹などの皮膚症状が副作用として現れる可能性があります。
座薬は挿入前に排便を済ませておくことと、挿入しやすい姿勢で入れるようにすると、薬剤が出てきてしまうなどのトラブルが避けやすくなります。
座薬は溶けやすく体内に吸収されやすいので、もし薬剤が出てきてしまっても新しい薬剤を入れるのは避けて、次の時間まで待つようにしてください。
副作用を避けるためにも、抗生物質の座薬は正しく使用しましょう。