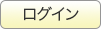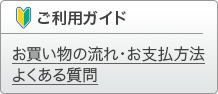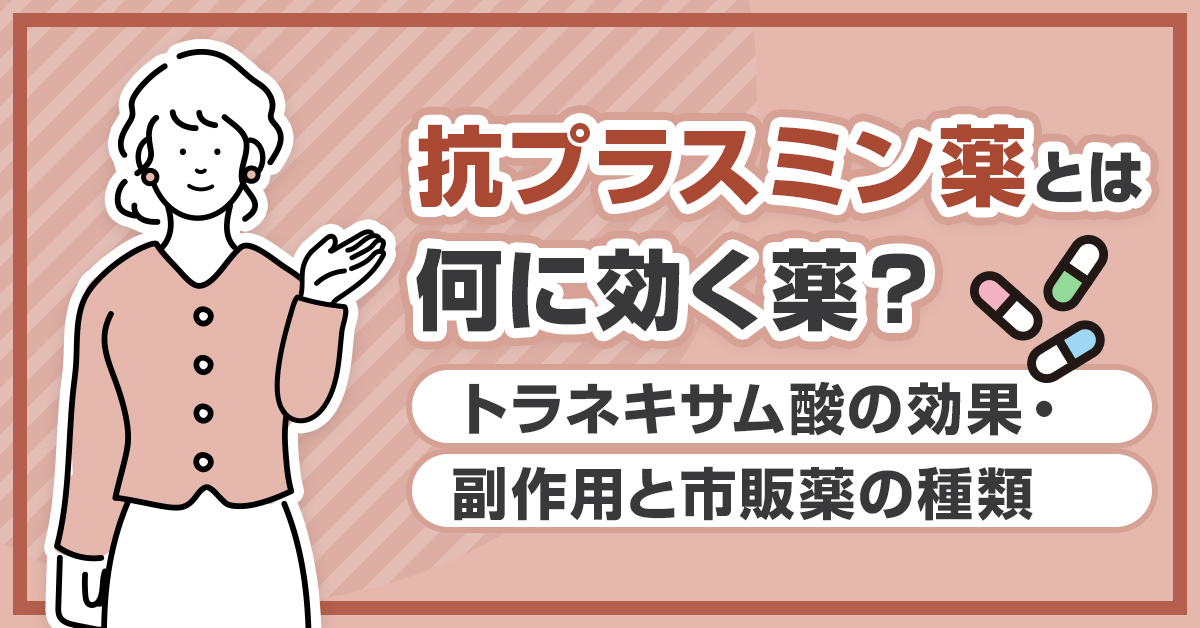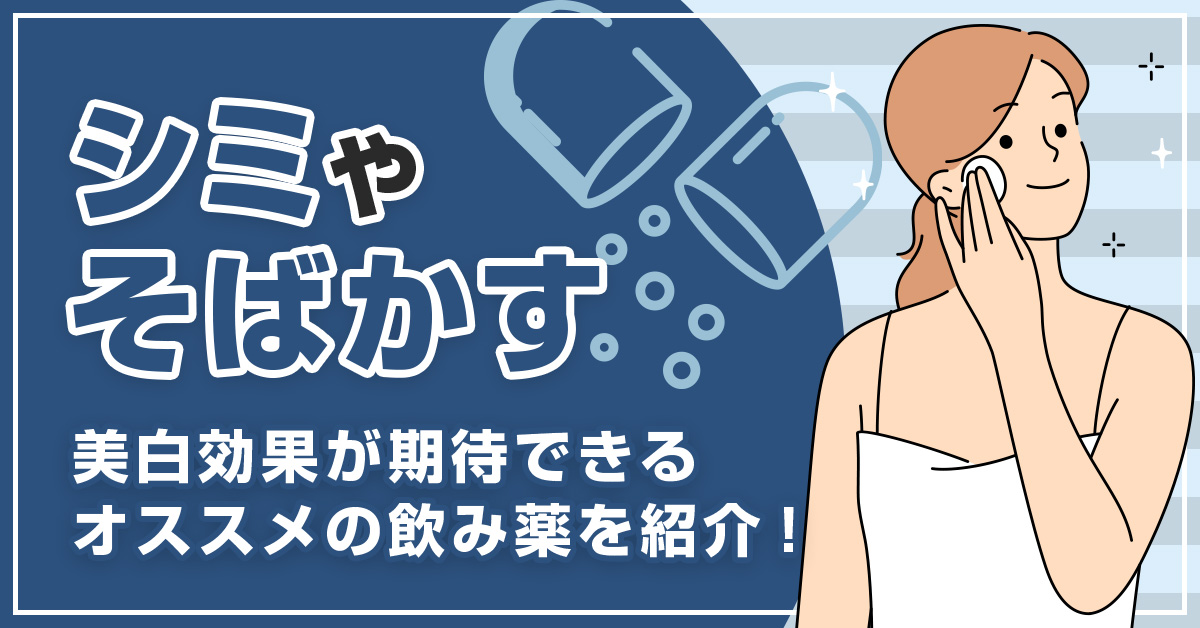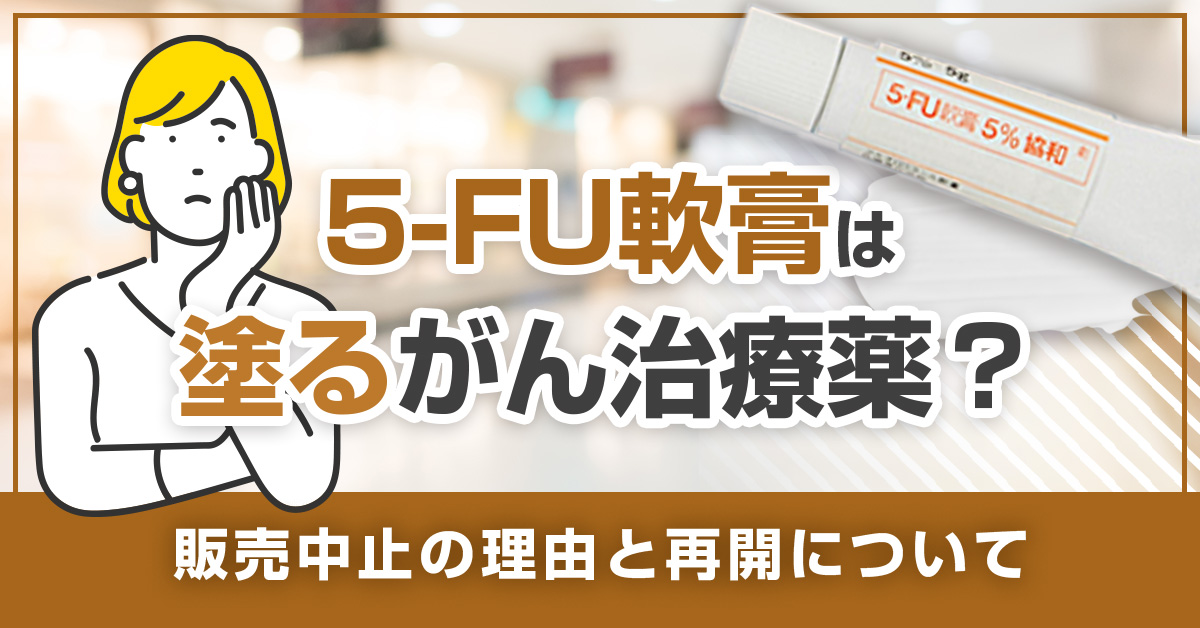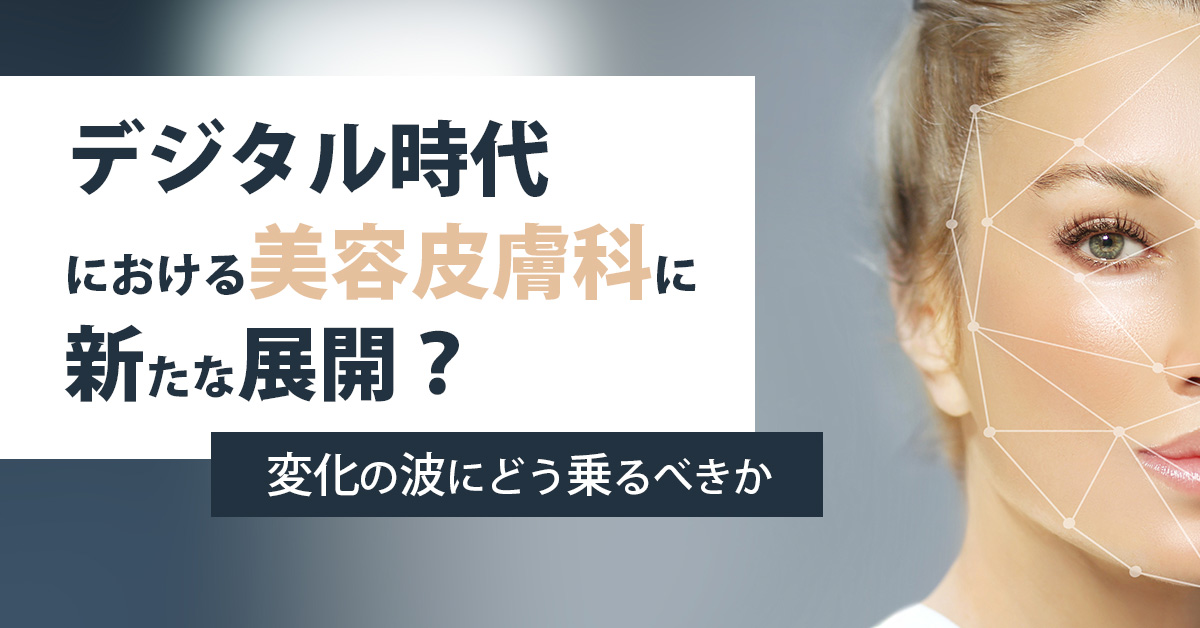トラネキサム酸を有効成分とした抗プラスミン薬は多種多様な効果があるため、様々な薬剤に配合されています。
しかしながら、一般的に名前を広く知られていない抗プラスミン薬について具体的なイメージが湧かないという方も多いのではないでしょうか。
ここではトラネキサム酸を配合した抗プラスミン薬の効果や副作用、使われている薬剤を紹介していきます。
抗プラスミン薬の作用について学んで正しく使用していきましょう。
抗プラスミン薬とは
トラネキサム酸が配合された抗プラスミン薬が持つ抗プラスミン作用は、体内で様々な効果を発揮してくれます。
ここでは抗プラスミン薬について理解しやすいように、まずプラスミンの作用について解説していきます。
プラスミンとは
血液には血管外に出た時に凝固して傷口を覆い、血液が体外に流れ出ることを防ぐ作用があります。
このような作用は過剰に血液を流失しないために必要な身体の仕組みですが、目に見える出血以外にも血管に細かい傷ができたり、何らかの理由で血流が悪くなったりする時には血管内でもこの作用が起こり、血液が固まってしまうことがあります。
これがいわゆる血栓です。
初期の血栓は小さくても、様々な要因によって大きく成長して血管を塞ぐようになると酸素や栄養素などが運べなくなって組織の壊死に繋がります。
そのため、身体には血栓を溶解するシステムが備わっているのです。
この血栓を溶解するシステムの1つが、血液中にできる血栓を溶かす働きを持つプラスミンと呼ばれるタンパク質分解酵素です。
通常、プラスミンは血栓の溶解という身体にとって重要な働きをしていますが、病気などによって働きが過剰になると、出血が止まらなくなってしまうといった症状を引き起こす原因にもなります。
このような場合には、大量の出血を防ぐためにプラスミンの働きを抑制して血を固まりやすくする処置を行う必要があります。
それに加えて、プラスミンは炎症作用にも影響を与える物質でもあり、喉の細胞がウイルスや細菌によって攻撃されるとプラスミンが発生します。
このプラスミンが炎症や痛みを起こす物質を発生させたり、血管を拡張したりして腫れや痛みなどの症状を引き起こすのです。
このような炎症を改善させる時にもプラスミンの発生や増殖を抑制する処置が有効となります。
抗プラスミン薬の効果
トラネキサム酸を始めとする抗プラスミン薬は、プラスミンが原因となる出血や炎症を抑える抗プラスミン作用を持つ物質です。
トラネキサム酸は次のような病気に使用されています。
- 手術における異常出血
- 白血病や再生不良性貧血などの出血傾向にある病気
- 肺出血や腎出血などの異常出血
- 扁桃炎や咽頭炎などの痛みや腫れ
- 口内炎における痛みや腫れ
- 蕁麻疹や薬疹といった皮膚症状
これらのプラスミンが関与している様々な症状の治療に抗プラスミン薬は使用されています。
しかしながら、抗プラスミン薬は抗生物質ではないので細菌の増殖を抑えるような効果はないことは覚えておく必要があります。
この他にも、トラネキサム酸にはプラスミン作用を阻害することでメラノサイトの活性化因子を抑制する効果もあると考えられています。
メラノサイトは紫外線やストレスなどの刺激を受けることで活性化してメラニン色素を生成し、シミの原因となる物質です。
このメラノサイトの活性化を抑制することに繋がる作用を持つトラネキサム酸は、肝斑や老人性色素斑などのシミの治療薬として医薬品に配合されたり、美白効果を期待して化粧品に配合されたりしています。
抗プラスミン薬の副作用
抗プラスミン薬のトラネキサム酸は比較的安全性の高い薬剤とされていますが、医薬品である以上は副作用が起こる可能性があることも理解しておきましょう。
抗プラスミン薬の副作用には、食欲不振や吐き気といった胃腸症状、かゆみや発疹といった皮膚症状などの副作用が起こる恐れがあります。
特に人工透析をしている患者さんが重篤な副作用である痙攣を引き起こしたケースが報告されているので、体調の変化が見られた場合には医療機関を受診してください。
また、抗プラスミン薬は出血を止める、つまり血を固まりやすくする作用があるため、血栓が問題となる血栓症や心筋梗塞、脳血栓、血栓性静脈炎などの病気を患っている場合は注意して使用しなければなりません。
それに加えて、妊婦の使用も禁忌となっています。
さらに飲み合わせの面では血栓ができやすくなってしまうため、止血薬であるトロンビンとの併用は禁止されている他、血栓リスクが上昇するピルとの併用にも注意が必要です。
トラネキサム酸を服用中に他の薬剤と併用を考えている場合には、副作用のリスクを避けるためにも医師や薬剤師に相談してください。
抗プラスミン薬の処方薬の種類
抗プラスミン薬の有効成分であるトラネキサム酸が配合されている処方薬には、多種多様な剤型があります。
まずトラネキサム酸が主成分の先発薬は第一三共のトランサミン錠500mgとトランサミンシロップ5%です。
それに加えて、第一三共からトランサミン散50%、トランサミン錠250mgの内服薬、トランサミン注5%、トランサミン注10%といった注射薬があります。
トラネキサム酸の後発品は陽進堂からトラネキサム酸錠250mg「YD」、日本新薬からトラネキサム酸カプセル250mg「NSKK」など複数の製薬会社から様々な剤型の薬剤が販売されています。
なお、これら処方薬には皮膚や喉などの炎症を抑えたり、出血を止めたりする効能はあるとされていますが、肝斑の改善については明記されていません。
トラネキサム酸が配合された市販薬の種類
抗プラスミン薬であるトラネキサム酸が配合された薬剤には市販薬もあります。
処方薬は個人に合わせて用量を調整できることから効果を重視しているのに対し、市販薬は老若男女、様々な体型の人が使用することを考慮して安全性を重視して作られています。
その分、処方薬よりも成分量を減らし、副作用のリスクを下げているという特徴がありますが、病院に行かなくても購入できる市販薬は忙しい現代社会において欠かせないものになっています。
ここでは薬局やドラッグストアで購入できるトラネキサム酸が配合された市販薬の種類について解説していきます。
市販薬は同じトラネキサム酸が配合されていたとしても、症状によって製品が異なります。
購入する際には自分の症状に合わせて薬剤を選んでいきましょう。
風邪薬
市販の風邪薬は様々な症状を総合的に改善していくために、様々な有効成分が配合されています。
抗プラスミン薬には炎症を抑制する効果があることから、トラネキサム酸が配合された薬剤には喉の痛みや腫れの改善が期待できます。
トラネキサム酸が配合された風邪薬の一例を挙げると、第一三共ヘルスケアのペラックT錠や全薬工業のジキニンFirstNEO錠などがあります。
ただし、風邪薬に配合されている成分によってはトラネキサム酸単独では見られなかった眠気などの副作用が現れる場合があります。
眠気の副作用がある薬剤を服用中は、乗り物の運転や機械の操作は禁止されているため、薬剤を選ぶ際には注意が必要です。
口内炎薬
口内炎の市販薬には内服タイプと患部に塗布または貼付するタイプがありますが、トラネキサム酸が配合された薬剤は内服タイプです。
炎症を起こすプラスミンに作用して、トラネキサム酸が身体の内側から働きかけてくれます。
市販の口内炎薬には第一三共ヘルスケアのトラフル錠があり、塗り薬や貼り薬、うがい薬と併用することも可能です。
肝斑治療薬
トラネキサム酸は肝斑の原因となるメラニンの生成を抑制する作用を持つとされているため、市販薬では肝斑の治療薬も販売されています。
30〜40代頃に両頬付近や額などに左右対称に突然現れるシミは肝斑であることが多く、くすみの原因になります。
一般的なシミの治療に使用しているレーザーで肝斑ができている細胞を刺激するとさらにメラニンを作って悪化させてしまう恐れがあることから、特別なレーザーを使用して治療する必要がありました。
このような性質を持つ肝斑には、内服薬による治療も効果的とされており、肌のターンオーバーを促しながら肝斑を改善へ導くことが期待されています。
お薬ネットでもトラネキサム酸を配合した海外の処方薬パウゼ10錠を通販で購入することが可能です。
パウゼ10錠はトラネキサム酸に加えて、L-システイン、ビタミンC、B6やパントテン酸カルシウムが配合されており、総合的に肌をケアできるのが特徴です。
2ヵ月継続して服用していくと肝斑が薄くなり効果が実感できるとされているので、肝斑でお悩みの方は一度ご相談ください。
抗プラスミン薬は止血・抗炎症効果のある薬
抗プラスミン薬はトラネキサム酸を主成分とした薬剤で、体内のタンパク質分解酵素であるプラスミンを抑制する効果を持っています。
プラスミンは血栓を溶かして血流を整える働きがありますが、病気などが原因となって過剰に作用するようになると出血が止まらなくなってしまいます。
このような場合に抗プラスミン薬を使用して、プラスミンを抑制することで止血を促します。
他にもプラスミンは炎症に影響を与えており、抗プラスミン薬によって扁桃炎や咽頭炎、口内炎などによる痛みや腫れなどを改善できます。
また、従来のレーザー治療では難しいとされている肝斑にもトラネキサム酸は有効です。
お薬ネットでも海外の処方薬であるパウゼ10錠を通販で購入することが可能なので、肝斑でお悩みの場合は一度ご相談ください。