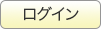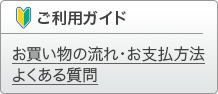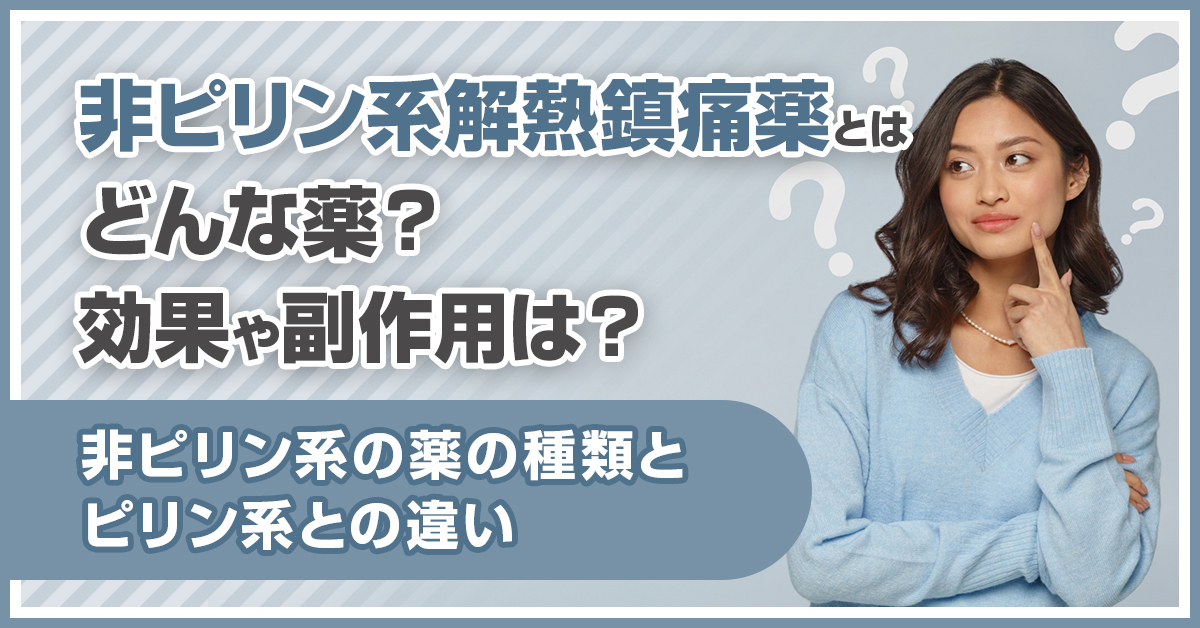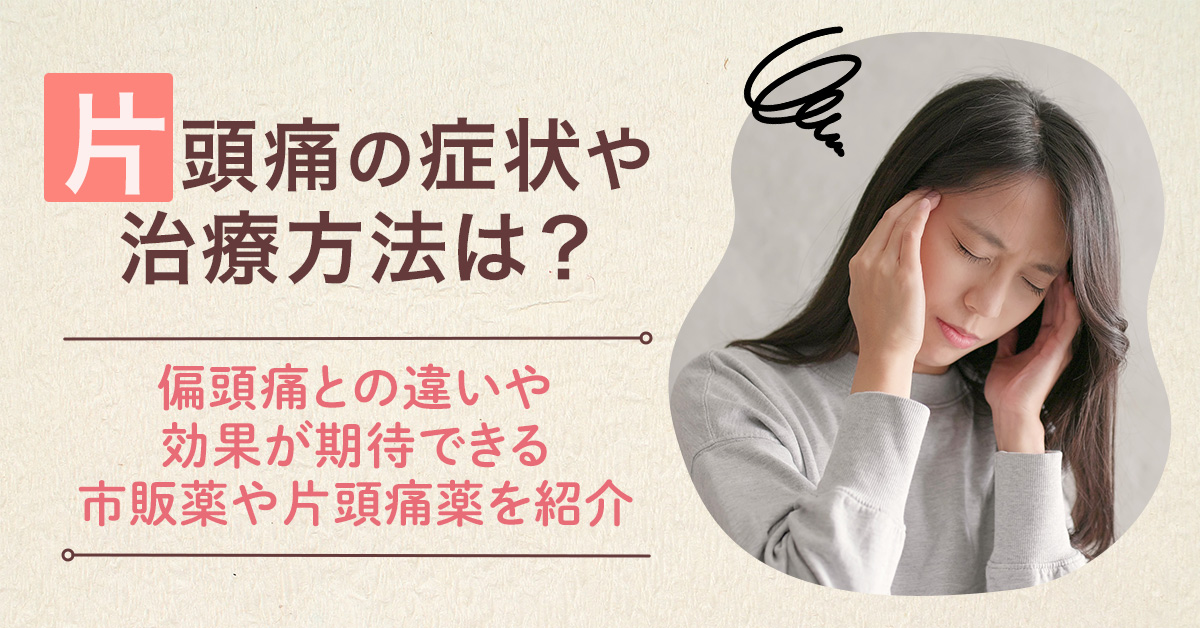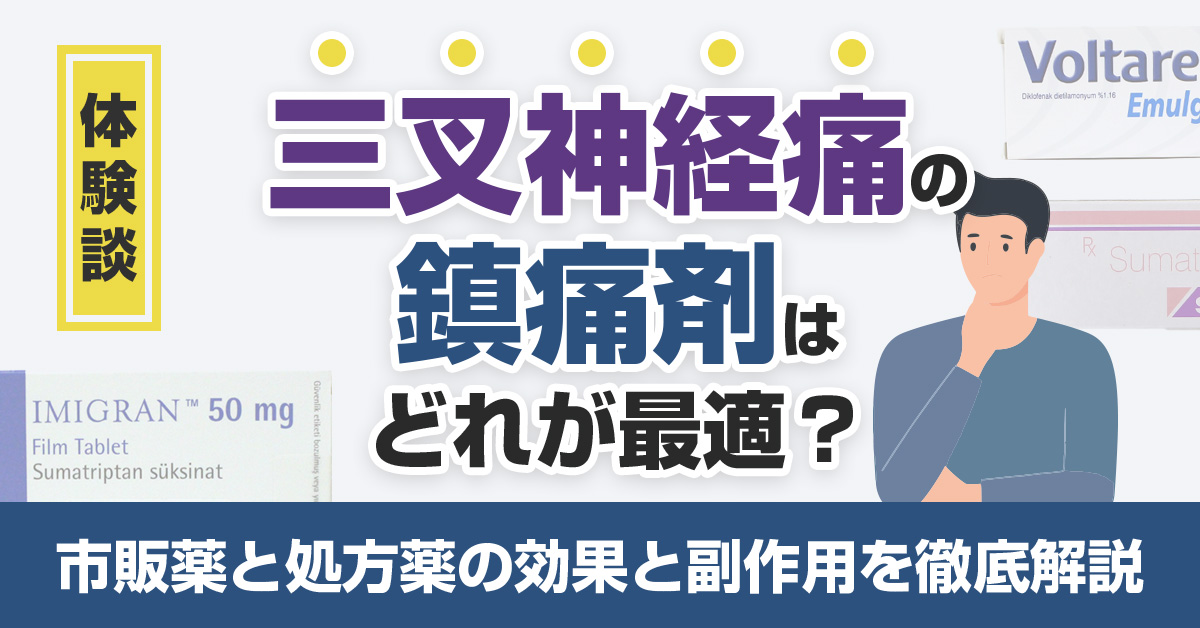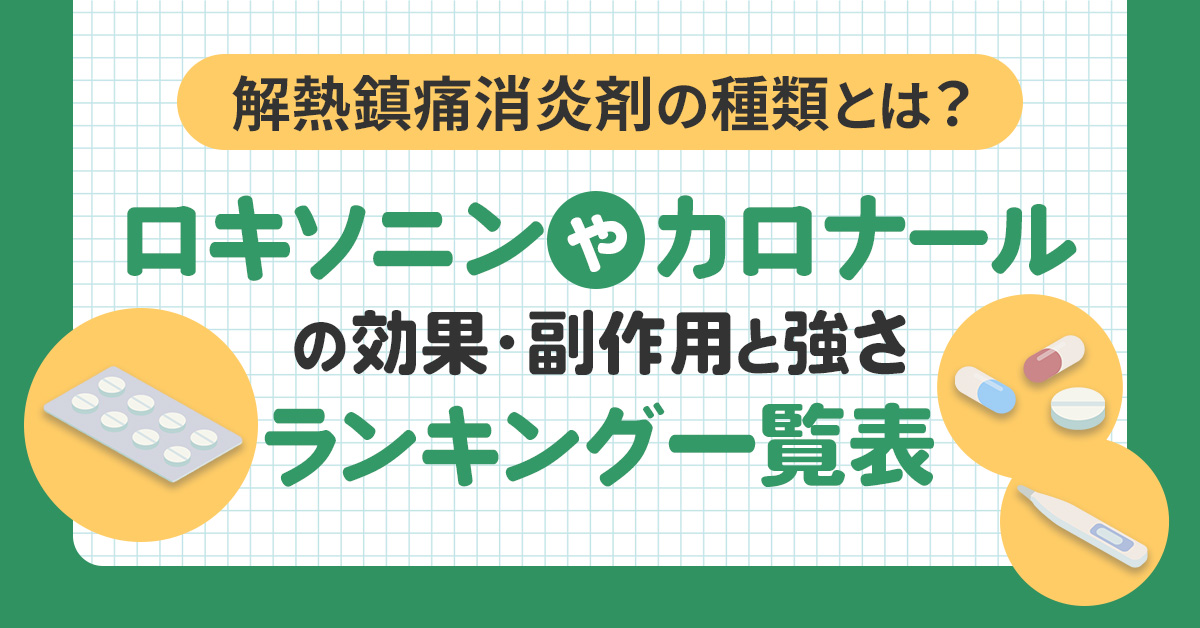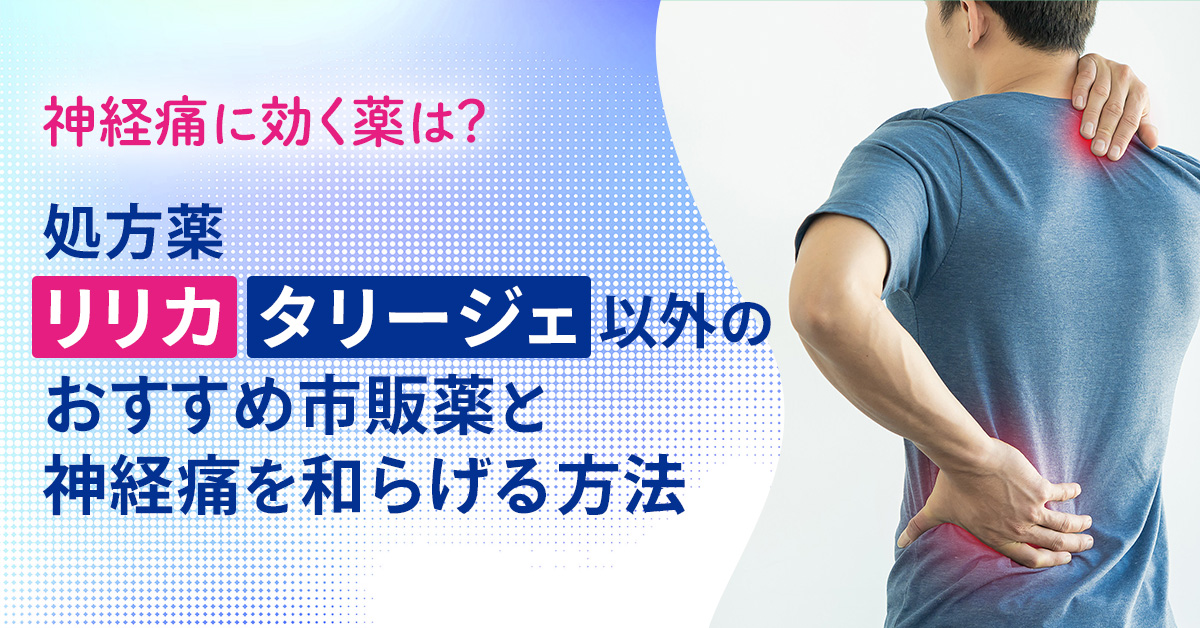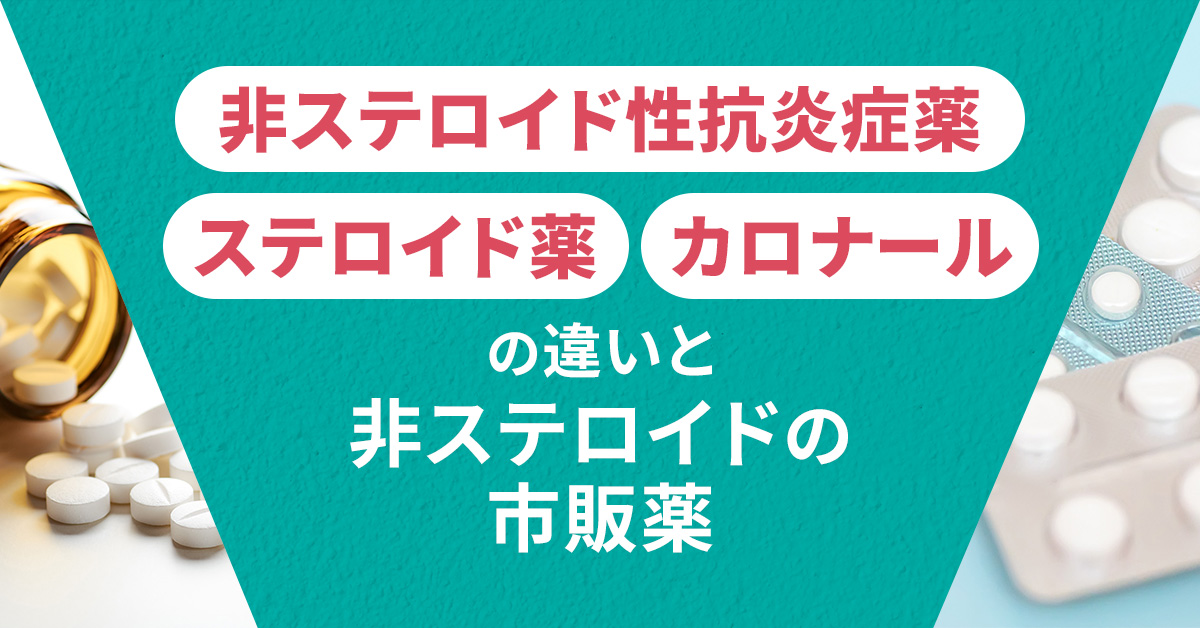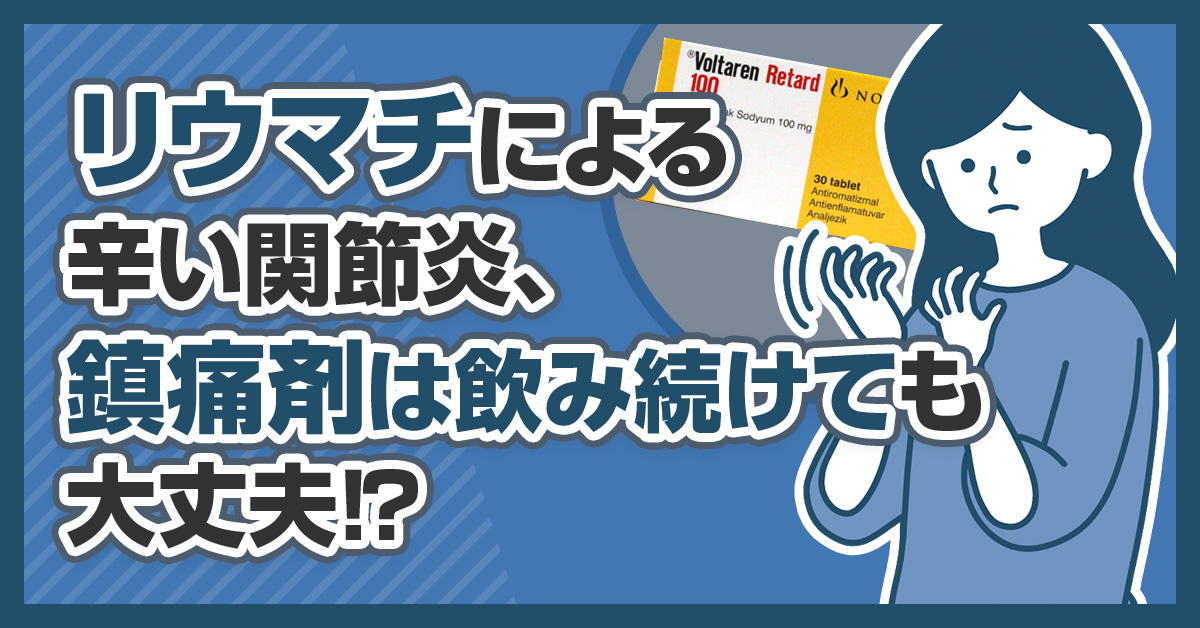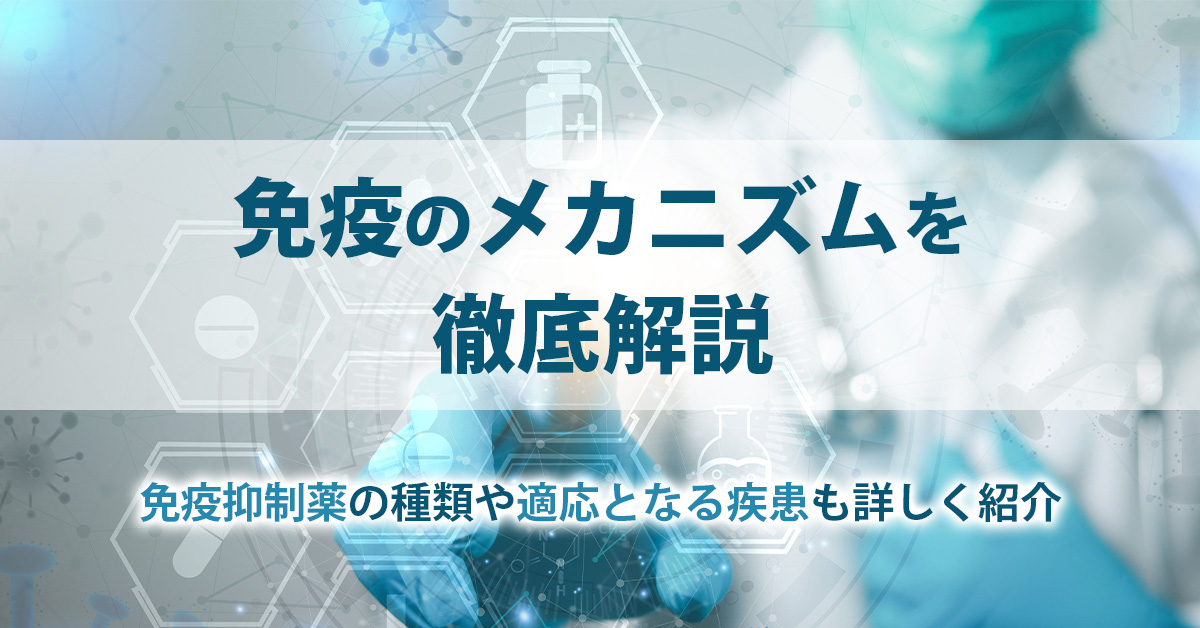高熱や痛みなどの症状を和らげる解熱鎮痛薬には、非ピリン系解熱鎮痛薬・ピリン系解熱鎮痛薬・非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の3種類があり、成分や効き目に違いがあります。
今回は解熱鎮痛薬の中の非ピリン系解熱鎮痛薬を中心に紹介していきます。
効果や副作用に加えて、非ピリン系解熱鎮痛薬の薬の種類やピリン系解熱鎮痛薬との違いについても解説していきますので、どの解熱鎮痛薬を使ったら良いか迷っている方はぜひ参考にしてください。
非ピリン系解熱鎮痛薬とは
非ピリン系解熱鎮痛薬はピリン系特有のピラゾロンという化学構造を持っていないことから、このように呼ばれています。
ここでは非ピリン系解熱鎮痛薬の効果や副作用について解説していきます。
非ピリン系解熱鎮痛薬の効果
非ピリン系解熱鎮痛薬の主成分であるアセトアミノフェンには、体温を上げる働きをもつ脳の視床下部の体温調節中枢に働きかけて熱を体外へ放出させる解熱作用と、痛みを伝える物質を阻害して痛みを緩和させる鎮痛効果があります。
アセトアミノフェンは平熱時に使用しても体温に影響を与えにくい特徴があるため、熱がない時の頭痛や生理痛の鎮痛にも使われています。
また、胃への負担が少なく、眠くなりにくいため、飲むタイミングを選ばないのもアセトアミノフェンのメリットと言えるでしょう。
ただし、抗炎症作用についてはほとんど効果が期待できないとされています。
非ピリン系解熱鎮痛薬の副作用
非ピリン系解熱鎮痛薬に分類されるアセトアミノフェンの副作用には吐き気や食欲不振などの消化器症状に加え、重篤な副作用として、ごく稀に肝機能障害やアナフィラキシーを引き起こす可能性があります。
倦怠感や黄疸などは肝機能障害の、蕁麻疹やかすれ声などはアナフィラキシーの初期症状の恐れがあるため、このような体調の変化が見られた場合には速やかに医療機関を受診してください。
こういった副作用の懸念からも過敏症や重篤な肝障害がある方、妊婦の使用は禁止されています。
また、アセトアミノフェンは小児や高齢者も使用できる薬剤ですが、副作用が起きていないか慎重に確認していくことが大切です。
非ピリン系解熱鎮痛薬の種類一覧
非ピリン系解熱鎮痛薬のアセトアミノフェンが含まれている薬剤は、シロップ、錠剤、散剤といった内服薬と挿入剤、静注液など多種多様な剤型が製造されています。
シロップ
シロップの内服薬には、東和薬品のアセトアミノフェンシロップ小児用2%「トーワ」、あゆみ製薬のカロナールシロップ2%、三和化学研究所のアセトアミノフェンDS40%「三和」などの処方薬があります。
シロップは薬に慣れていない小さな子どもでも飲みやすいのがメリットです。
散剤
散剤の先発薬はシオノギファーマのSG配合顆粒ですが、アセトアミノフェンの他にピリン系であるイソプロピルアンチピリンやアリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェインも一緒に配合されています。
散剤の後発品は長生堂製薬のアセトアミノフェン「JG」原末、あゆみ製薬のカロナール細粒20%、岩城製薬のピレチノールなどです。
錠剤
アセトアミノフェンが配合された錠剤には先発薬のヤンセンファーマのトラムセット配合錠ですが、こちらの薬剤にはトラマドール塩酸塩も配合されているので、トラマドールの副作用である眠気や吐き気などに注意が必要です。
後発品として日医工岐阜工場のアセトアミノフェン錠200mg「NIG」、あゆみ製薬のカロナール錠200、第一三共エスファのトアラセット配合錠「DSEP」などの他にも多くの薬剤が販売されています。
挿入剤
肛門に挿入して使用する挿入剤は先発薬が多く、久光製薬のアルピニー坐剤100やヴィアトリス製薬のアンヒバ坐剤小児用100mg、あゆみ製薬のカロナール坐剤100といった商品があります。
後発品には長生堂製薬のアセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」の他、様々な製薬会社から挿入剤が販売されています。
静注液
静注液は先発薬のテルモが販売しているアセリオ静注液1000mgバッグがあり、内服薬や挿入剤の使用が難しい場合に使用されます。
アセリオは乳児から使用することが可能です。
非ピリン系解熱鎮痛薬が購入できる場所
非ピリン系解熱鎮痛薬は病院処方の他に、薬局やドラッグストアで市販薬を購入することも可能です。
ただし、市販品にもアセトアミノフェンだけを有効成分としている薬剤と、イブプロフェンや非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)といった他の成分も配合されている薬剤があります。
得たい効果や副作用などは成分によって異なるため、注意して選びましょう。
また、病院で処方してもらう医療用医薬品と市販薬である一般用医薬品は同じ名前の薬剤であっても効き目や有効成分が異なる場合があります。
医療用医薬品は医者が患者さんに合わせて処方できるため、市販薬よりも強い効果が期待できるのが特徴ですが、市販薬である一般用医薬品は安全性が最優先されているために医療用医薬品よりも有効成分の含有量が少ないケースが多くなっています。
このような理由からも効果を重視したい場合には市販薬ではなく、病院で薬を処方してもらう方がよいと言えます。
しかしながら、処方薬がほしいけれど病院へ行くのが難しいという悩みもあるかもしれません。
このような場合には、海外で使われている医薬品を個人輸入代行のお薬ネットで購入することも可能です。
薬剤でお悩みの時には一度ご相談ください。
非ピリン系解熱鎮痛薬以外の薬
非ピリン系解熱鎮痛薬以外にもピリン系解熱鎮痛薬や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)という解熱や痛みを抑える作用を持つ薬剤があります。
ここではピリン系解熱鎮痛薬と非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の2種類を紹介していきます。
ピリン系解熱鎮痛薬
ピリン系解熱鎮痛薬はピラゾロンという化学構造を持った化合物で、イソプロアンチピリン、スルピリン、アミノピリンがありましたが、アミノピリンは発がん性物質を生成することが判明したため、世界的に医薬品への使用は禁止されました。
ピリン系解熱鎮痛薬は非ピリン系解熱鎮痛薬よりも解熱作用が強く、さらに抗炎症作用もありますが、副作用としてピリン疹と呼ばれる薬疹やアレルギーが見られることが多かったため、処方薬として使用されることが減りました。
このような経緯もあって現在、日本で使用されているピリン系解熱鎮痛薬はイソプロアンチピリンのみです。
イソプロアンチピリンが配合されている市販薬には、第一三共ヘルスケアのサリドンAやシオノギヘルスケアのセデス・ハイがあります。
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)はステロイド剤ではない解熱鎮痛薬です。
体内で痛みや炎症、高熱などを引き起こす原因物質であるプロスタグランジンを生成するCOXを阻害することで、解熱、鎮痛、抗炎症作用を発揮します。
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)には、ロキソプロフェンナトリウムが主成分のロキソニン、アスピリンが主成分のアスピリン、セレコキシブが主成分のセレコックス、ジクロフェナクナトリウムが主成分のボルタレン、ナプロキセンが主成分のナイキサンといった商品があり、少しずつ効果が異なります。
例えば、アスピリンは川崎病の治療や低用量で血流を良くする作用があり、ナイキサンは痛風や偏頭痛に対して高い効果を発揮するのが特徴です。
ただし、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)のCOX阻害作用によって気管支収縮が起こりやすくなるため、喘息発作を引き起こす可能性があります。
特にアスピリンが配合されている薬剤では非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)に対するアレルギーによって、アスピリン喘息という重度の喘息を引き起こすことがあるため、呼吸が苦しかったり、ゼーゼーしたりする症状が現れた時には速やかに医療機関を受診してください。
他にも、腹痛や吐き気などの消化器症状が現れることもあります。
また、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)で注意したいのが、インフルエンザの時に使用するとインフルエンザ脳症やライ症候群などのリスクが高まることです。
このような事態を避けるためにも、インフルエンザが疑われる時の解熱には非ピリン系解熱鎮痛薬のアセトアミノフェンを使用するのが一般的です。
非ピリン系解熱鎮痛薬はアセトアミノフェンが配合された薬
非ピリン系解熱鎮痛薬にはアセトアミノフェンを主成分としたカロナールやアセトアミノフェン、アルピニー、アンビバ、アセリオといった薬剤があり、熱を下げたり痛みを緩和したりする作用があります。
抗炎症作用はほとんど期待できませんが、平熱時に使用しても体温に影響を与えにくいため、頭痛薬や生理痛薬として使用されるケースも多いのが特徴です。
剤型も散剤や錠剤、シロップなどの内服薬に加え、挿入剤や静注剤があり、服用が難しい状態でも座薬や点滴などとして使用できます。
解熱鎮痛薬で見られることの多い消化器症状の副作用は少ないとされていますが、体質によっては吐き気や食欲不振などの副作用が現れることがあります。
さらに重篤な副作用として肝機能障害やアナフィラキシーを引き起こす可能性もあるため、体調に違和感が現れた時にはすぐに医療機関を受診してください。
また、解熱鎮痛薬には非ピリン系解熱鎮痛薬の他に、ピリン系解熱鎮痛薬と非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)があるので、病気や症状ごとに使い分けていくとよいでしょう。